1.「基礎能力検査」とは何か?
基礎能力検査は、受験者の基礎学力や性格特性を測定するために実施される検査です。
言語理解力、数的処理能力、論理的思考力などの基礎的な能力や、性格傾向を評価することを目的としています。
もともと公務員試験では「教養試験」がありますが、それに近い内容です。
一般に就職・転職活動をする人には馴染みがあるSPIも基礎能力検査の1種。
SPIなどを導入することで、より多くの受験者を呼びこもうとする自治体が増えています。
基礎能力検査を課す自治体【けっこうあります】
| 基礎能力検査の種類 | 主な実施自治体 |
| SPI | 横浜市、国分寺市、一部の県庁等 |
| SCOA | 市原市、柏市、一部の県庁等 |
| GAB | 武蔵野市、町田市、一部の県庁等 |
※実施科目は、年度によって変わる可能性があります。必ず、各自治体の最新の「募集要項」を確認してください。
上の表に示した通り、基礎能力検査を経験者採用で実施している自治体は少なくありません。
従来の教養試験のかわりに実施している自治体が多いようです。
実施タイミングは1次試験が多いですね。
面接や論文といった人物試験を丁寧に実施するため、事前に受験者をある程度絞りこみたいという自治体側の意図もありそうです。
【注意】面接や論文ほど重要ではないが対策ゼロは危険
「SPIとか大学時代にやったなぁ。」
「ほとんど対策しなくてもいけた気がするけど。」
こんなふうに思われる方もいるかもしれません。
たしかに、基礎能力検査は「足切り」の要素が強く、面接や論文ほど最終合格に直結しないです。
ただ、まったく対策しないのは危険です。
たとえば横浜市(社会人採用・R6春試験)では、SPIを実施した1次試験の合格者は、246人中155人でした。
実に4割近くの受験生がSPIで落ちてしまっているんです。
この中には、その後の試験対策をしっかりしていた受験生もいたはず…。
基礎能力検査が課される自治体を受験する方は、努力がしっかり報われるように、基礎能力検査もキチッと対策しておきましょう。
2.「基礎能力検査」の種類別解説
では、基礎能力検査にはどのようなものがあるのでしょうか。
現状、公務員試験の経験者採用でよく使われている基礎能力検査は次の3つです。
・SPI(リクルートマネジメントソリューションズ)
・SCOA(日本経営協会総合研究所)
・GAB(日本エス・エイチ・エル)
これらの基礎能力検査、全体として、
✓問題自体は、一般的な教養試験よりもカンタン
✓その分、解答時間が短く、処理スピードが試される
✓Webテスト形式もある(採用自治体も多い)
以上のような傾向があります。
教養試験と同じスピード感で解くと時間切れになり、本来の実力が発揮できないかもしれません。
実際に、各テストの問題数や試験時間を確認してみましょう。
| 検査名 | 問題数 | 試験時間 |
| SPI | 60問程度
※Webテストやテストセンター方式の場合、受験者の回答状況により問題数が変わる |
35分
※Webテストやテストセンター方式の場合、1問ごとに制限時間あり |
| SCOA | 120問 | 60分 |
| GAB | 92問 | 60分 |
大体、1問1分で解かないといけない計算ですね。
SPIの言語分野やSCOAはさらに厳しく、1問20~30秒で解答することが必要です。
ですから、本番に近い問題で練習しておくことが大切です。
(本記事後半で、具体的な練習法を解説します!)
では続けて、それぞれのテストの特徴を紹介していきますね。
SPI(リクルートマネジメントソリューションズ)
| 検査名 | 問題数 | 出題分野/試験時間 |
| SPI | 言語40問、非言語20問程度
※Webテストやテストセンター方式の場合、受験者の回答状況により問題数が変わる |
言語,非言語/35分
※Webテストやテストセンター方式の場合、1問ごとに制限時間あり |
SPIは、リクルートマネジメントソリューションズが提供する検査です。
SPIでは、言語能力及び非言語能力を問う問題が出題されます。
ペーパーテストよりもWebテストやテストセンター方式(決まった会場でPCを使って回答する)が主流で、その場合、1問ごとに制限時間があります。
また、回答状況により、問題数や問題の難易度が変わっていきます。
序盤に間違いが多いとその後の問題が簡単になり過ぎて、最終的にたくさん正解しても評価されづらいということもあるので注意が必要です。
参考書のオススメは、『これが本当のSPI3だ! 』です。
SCOA(日本経営協会総合研究所)
| 検査名 | 問題数 | 出題分野/試験時間 |
| SCOA | 120問 | 言語,数理,論理,常識,英語/60分 |
SCOAは、もともと1985年に開発された歴史ある適性検査です。
「言語,数理,論理,常識,英語」の5分野の問題で構成されています。
SCOAの特徴はなんといっても問題数の多さです。
60分で120問解くということで、常に1問30秒の解答速度が求められ、試験終了後にはかなり疲れを感じる人が多いはず。
問題の難易度は高くないので、処理能力を問われている試験といっても良いでしょう。
試験前に、60分取り組む”スタミナ”をつけておく必要がありますね。
参考書は、『公務員試験で出る SPI・SCOA[早わかり]問題集』などが良いでしょう。
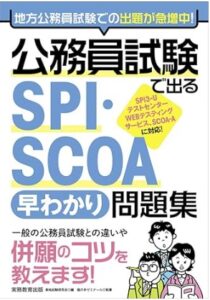
SPIと一緒に対策できる優れもので、どちらも対策しなければいけない方には特にオススメの一冊です。
GAB(日本エス・エイチ・エル)
| 検査名 | 問題数 | 出題分野/試験時間 |
| GAB | 言語理解52問
計数理解40問 |
言語理解/25分
計数理解/35分 |
GABは日本エス・エイチ・エル社が開発した検査です。
GABは適性検査の中では比較的、問題の難易度が高いと言われています。
特に図表を多く用いた資料問題に、多くの受験生が時間を取られるでしょう。
そのため、試験全体の時間配分も難しく、事前の練習が必須です。
『これが本当のCAB・GABだ! 』などの本で、本番と同じ試験時間で練習してください。
※この本はけっこう分厚いですが、CAB(GABと似た試験でIT企業などで良く使われるもの)についての対策ページが半分を占めているので、実際に勉強するのは残り半分だけで大丈夫です。
3.タイパを意識した「基礎能力検査」対策のコツ
「試しに解いてみたら、たしかに時間が足りない…」
「論文や面接の対策もあるし、困ったなぁ…」
「基礎能力検査」に向けて対策するとしても、使える時間は限られていますよね。
そこで、本記事では短期間で「基礎能力検査」対策を仕上げていくコツを4つお伝えします。
結論、次の4点を意識して勉強してみてください。
①いきなり実践形式で、時間を測って解くこと
②「少し勉強すればできる」ところを狙って勉強
③「少し勉強すれば早くなる」ところを狙って勉強
④(Webテストの場合)パソコンで解答する練習をする
以下、1つずつ解説します。
【対策のコツ①】いきなり実践形式で、時間を測って解くこと
先ほど、各種問題集を紹介しました。
それぞれの問題集は【分野ごとの練習問題→1,2回分の本番模擬問題】という順番で作られています。
短期間で実力アップを目指すなら、「1,2回分の本番模擬問題」から解きましょう。
つまり、”問題集を後ろから使う”ということです。
本番通りに時間を測って、どんどん解きます。
このとき、問題ごとにかかった時間をメモしておくと、あとで自己分析しやすいのでオススメです。
先に紹介したように、「基礎能力検査」は問題それぞれの難易度は高くありません。
ただ、それぞれの問題にどれくらい時間がかかるかは、人によってけっこう違いがあります。
そこを把握することで、最も効率よく得点力を伸ばせるのです。
【対策のコツ②】「少し勉強すればできる」ところを狙って勉強
ステップ1で1回分の問題を解いたら、すかさず答え合わせをします。
この時、〇と×をつけるだけでは伸びません。
たとえば、次のような4種類の印をつけます。
| ◎ | 途中の解法も含めてばっちり |
| 〇 | 途中の解法は不完全だが結果的に正解 |
| △ | 途中の解法は合っていたが結果的に不正解 |
| × | まったく見当外れのバツ |
ずばり、〇△の分野の対策が伸びるポイントです。
〇は、途中の解答根拠も含めて、ばっちり◎になるように。
△は誤答になってしまった分岐点を確認し、同種の問題が出たら確実に正答できるように練習します。
模擬問題の解き直しだけでは練習量が足りません。
そこで、このタイミングで問題集の前半部分の「練習問題」を使います。
ただ、これも最初から全ページを解くのではありません。
〇や△のような、「あと少しで得点が安定する・伸びる」分野のページを集中的に解くのです。
※試験までに余裕があれば他のページにも取り組んでよいでしょう。
ただ、このような苦手分野は対策に時間がかかるので、優先度としては低くなります。
また、◎のような得意分野は、基本的に対策する必要はありません。
(後述するような「時短解法」を探す場合は除きます。)
【対策のコツ③】「少し勉強すれば速くなる」ところを狙って勉強
また、「1問ごとの解答にかけた時間」を確認し、そこから戦略を練ることも大切です。
まず、自分が得意で、より早く解けそうな分野は”時短”を目指します。
たとえば数的処理が得意な人は、問題を見た瞬間に、ある程度「答えはこの選択肢じゃないかな?」と予想できるときがあります。
そんなとき、実際にその選択肢の数値を”代入”してみて正答であることができれば、かなり短時間で解答できます。
このような時短の積み重ねで、得点力はアップしていきます。
逆に、自分にとって大の苦手分野、得点できない分野については、「深追いしないこと」も戦略の一つです。
つまり、時間をかけ過ぎないようにするんです。
場合によっては、「30秒で自信がもてなかったら勘で解いて次へ進む」というようにマイルールを作ってもいいでしょう。
ただし、もちろんのことですが、そんな”特例”は1分野、一回のテストで1,2問程度に留めましょう。
※もし、全般的に得点が振るわず、それでも「基礎能力検査」を使う自治体の志望度が高い場合には、じっくり時間をかけて対策する必要があるでしょう。
その際は、問題集を2,3か月かけて、「最初から1ページずつ解く」勉強法も必要です。
【対策のコツ④】(Webテストの場合)パソコンで解答する練習をする
また、Webテストの場合、本番同様にPC画面に問題を表示して解く練習をした方がよいです。
実はWebテストは、カンタンな計算なら暗算してしまうのがコツです。
というのも、途中計算などを手元の紙にメモすると、視線が手元のメモとPC画面を往復することになり、時間を大きくロスしてしまうからです。
ですから、Webテストでは手元にメモ用紙は用意しておきつつ、基本的にはディスプレイをずっと見ながら解答する癖をつけると良いです。
ただ、ここで問題になるのは、Webテストを対策するにしても情報が充実しているのは紙の書籍だということです。
電子書籍化されている参考書を使うか、自分で紙の書籍をPDF化して、PC画面に表示して学習する必要があります。
ちなみに私はかつて、スマホのスキャンアプリを用いて参考書の写真をPCに取り込み、ディスプレイに表示して解く練習をしていました。
おかげで本番では緊張することもなく、無事、選考を通過しました。
手間はかかりますが、それだけの成果が出る学習法です。
4.まとめ
本記事のまとめです。
✓基礎能力検査で”対策ゼロ”は危険
✓希望自治体の基礎能力検査の種類を調べておくこと
✓SPI、SCOA、GABは、教養試験以上に「スピード勝負」
| 検査名 | 問題数 | 試験時間 |
| SPI | 60問程度
※Webテストやテストセンター方式の場合、受験者の回答状況により問題数が変わる |
35分
※Webテストやテストセンター方式の場合、1問ごとに制限時間あり |
| SCOA | 120問 | 60分 |
| GAB | 92問 | 60分 |
✓効率の良い勉強法のコツ4選
①いきなり実践形式で、時間を測って解くこと
②「少し勉強すればできる」ところを狙って勉強
③「少し勉強すれば早くなる」ところを狙って勉強
④(Webテストの場合)パソコンで解答する練習をする
以上です。
本記事が、あなたの学習のお役に立てば幸いです。
ASK公務員では「経験者採用」に関する情報提供を積極的に行っています。
勉強の合間に、以下の記事もお読みになってください。
| 【特別区経験者採用】知らないと差がつく!職務経歴書(エントリーシート)のポイント 【特別区経験者採用】サクッとわかる教養試験の勉強法 【特別区経験者採用】サクッとわかる職務経験論文の対策法 【特別区経験者採用】サクッとわかる課題式論文の対策法 【特別区経験者採用】かしこく併願戦略を立てよう~やりたいこと&科目&日程で考える |

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ
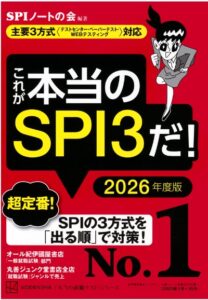
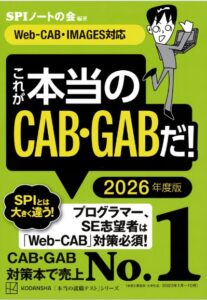
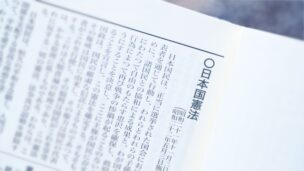
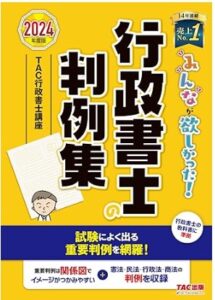
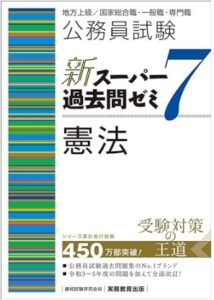
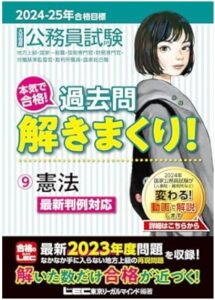
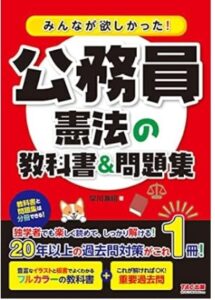
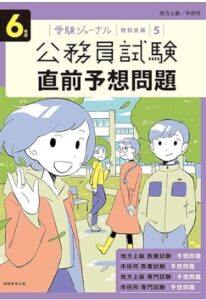
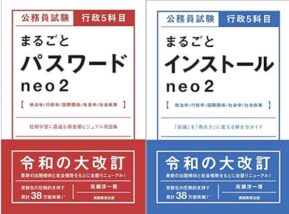
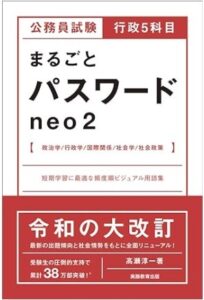

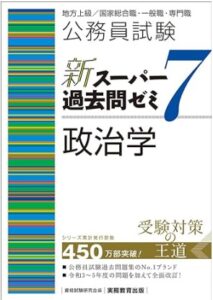

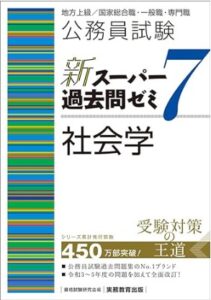
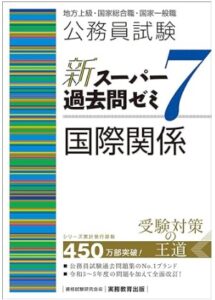
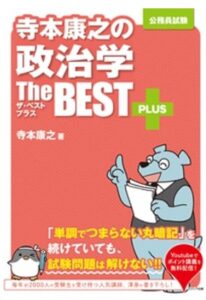

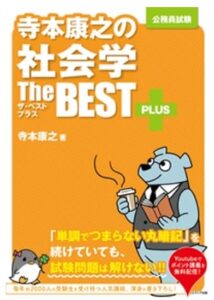


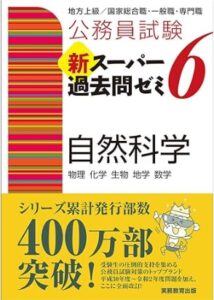
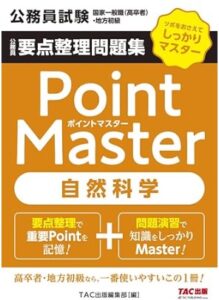
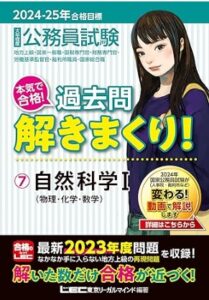
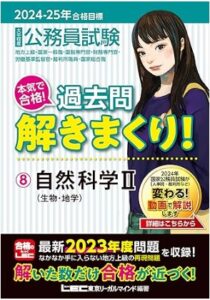

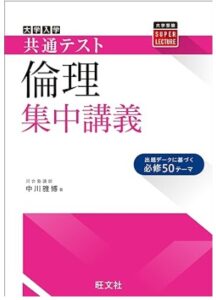

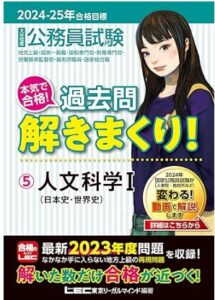

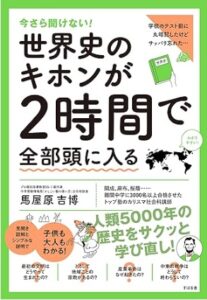

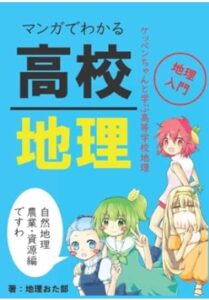



-1024x839.png)
-1024x590.png)
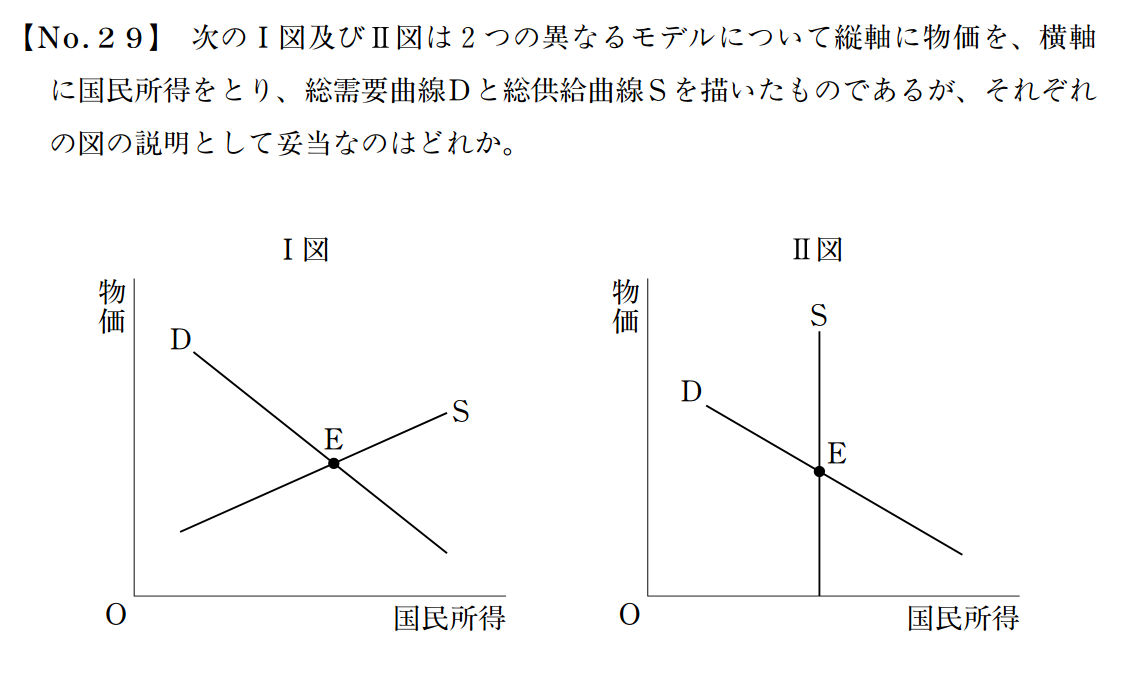
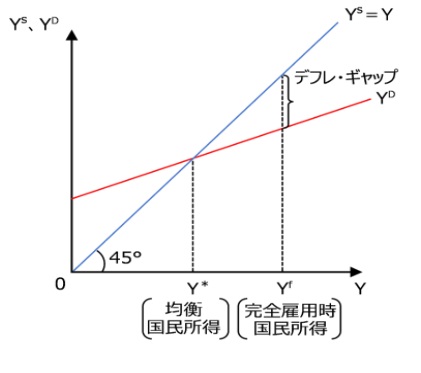


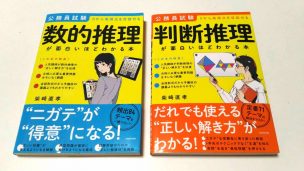
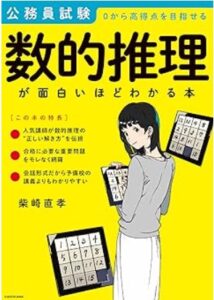
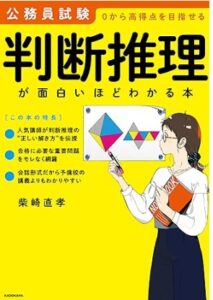
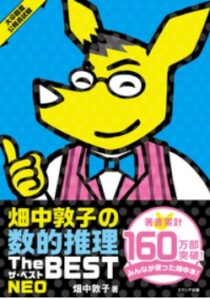
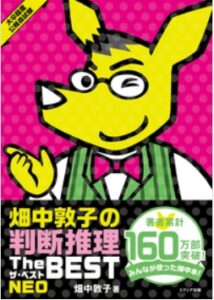
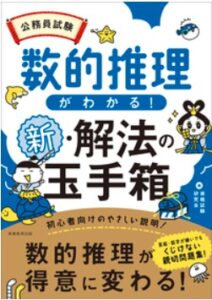
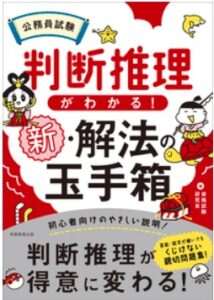
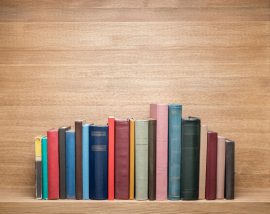


![速読英単語 (1)必修編 [改訂第6版]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51gPgv1YV%2BL._SL160_.jpg)

![話題別英単語 リンガメタリカ [改訂版]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51PKA8VY2YL._SL160_.jpg)












