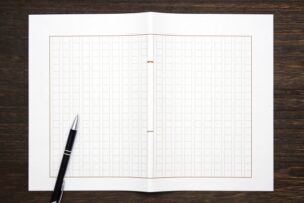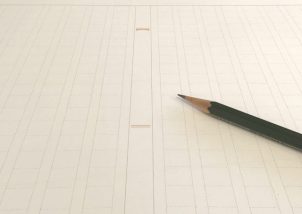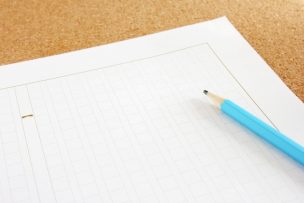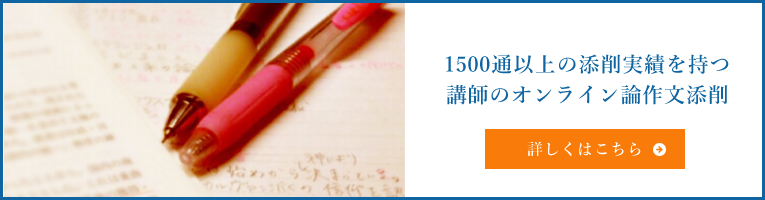こんにちは ASK公務員/究進塾 編集部です。今回は、栄養士公務員行政栄養士を目指す方のための論文対策講座についてのご紹介です。講座の受講を検討している方はぜひご参考にしてください。
論文試験対策
【論文対策】神奈川県庁 出題傾向と論文の構成
【論文対策】神奈川県庁 出題傾向と論文の構成
こんにちは。ASK公務員/究進塾 編集部です。今回は、神奈川県の公務員試験における論文対策について、過去問の傾向や効果的な構成方法を交えて、丁寧に解説いたします。
神奈川県の論文試験とは?
試験概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象区分 | 大学卒業程度(Ⅰ種試験・行政) |
| 試験時間 | 90分 |
| 指定字数 | 1,200字程度 |
試験時間と字数は比較的ゆとりがあるため、しっかりと構成を練ることが合格へのカギとなります。
出題傾向と2023年の論文テーマ
2023年度の出題例
政府は、令和4年10月28日に「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を閣議決定した。そこではリスキング※への支援強化など、「人への投資」の施策の拡充を掲げている。
このように「人への投資」が必要である社会的な背景や課題に触れながら、社会全体としてどのような取組が必要であるか、あなたの考えを論じなさい。
※リスキング:新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること(経済産業省HPより抜粋)
効果的な論文作成の手順
ステップ①:メモのメモを作成する
論文の構成を考える前に、思いついたことを箇条書きで列挙します。段落の構成を気にせず、「人への投資」に関する背景や課題、社会全体・神奈川県で取り組むべき内容を10個以上書き出しましょう。
ステップ②:構成メモを作成する
次に、段落構成を決めて論文全体の流れを組み立てていきます。1,200字程度なら5~6段落構成が適当です。
| 段落 | 記述内容 |
|---|---|
| 第1段落 | 現状の説明 |
| 第2段落 | 社会的な背景や課題の整理 |
| 第3段落 | 日本全体で取り組むべき施策 |
| 第4〜6段落 | 神奈川県で取り組むべき対策を2~3つ、段落ごとに述べる |
取り上げる施策が多いほど1つあたりの字数は短くなります。2つに絞るなら、内容をより深く掘り下げましょう。
ポイント:グルーピングと取捨選択
メモが多くなると、構成メモ作成時にいくつかのネタを「捨てる」必要があります。尾川講師は、これを「グルーピング」と呼び、複数のアイデアを1つにまとめる作業を推奨しています。
過去の出題テーマ(参考)
| 年度 | テーマ |
|---|---|
| 2022年 | 孤独・孤立対策 |
| 2021年 | 格差社会への対処 |
神奈川県では、日本社会が抱える社会問題をテーマにした出題が多い傾向にあります。日頃から社会問題や県の施策に注目しておくことが対策になります。
おわりに
ASK公務員/究進塾では、神奈川県を志望する方への過去問指導や添削サポートを行っております。技術職・中途採用の方の対策も充実しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
◆ 尾川講師の授業の特徴
この記事は、ASK公務員/究進塾 尾川直子講師の解説動画をもとに作成しています。講義や講師の雰囲気を知りたい方は、ぜひ動画をご覧ください。
【公務員試験】論文が苦手な人でも「自分の論文」が書けるようになる3ステップ学習法
「論文が苦手でやる気が起きない…」
「重要だとは分かっているんだけどな…」
「論文が苦手な人はどんな勉強をしたらいいの?」
こんな悩みや疑問に応える記事です。
本記事を読んで分かることは、次の通りです。
✓論文が苦手な人にありがちな3つの状況
✓論文が苦手な人もできる3ステップ勉強法
論文が苦手な方でも、今から頑張って合格を勝ち取るために必要な情報をこの記事につめこみました!
サクッと読める分量なので、学習の合間などに読んでみてくださいね。
それでは、いってみましょう!
1.【あなたは当てはまってない?】論文が苦手な人にありがちな状況3選
「他の勉強に比べて、論文の勉強ってやる気が起きないんだよね…。」
あなたは、こんなふうに思っていませんか。
私も受験生の頃、まったく同じ気持ちだったので良くわかります。
論文学習は、受験生に敬遠されがちな理由がいくつもあります。
×自己採点しづらい
×慣れない手書きで疲れる
×1本の論文を書くには、まとまった時間が必要
そのため、無意識に「論文学習を回避してしまう」受験生がとても多いんです。
以下、具体例を挙げますので、あなたも当てはまっていないかセルフチェックしてみてくださいね!
【その1】教養試験の勉強ばかりする
一番、よくあるパターンは教養試験の勉強に逃げてしまうこと。
教養試験の勉強は、先ほど挙げた論文学習のデメリットが少ないです。
自己採点できて、1問解くだけならスキマ時間にサクッと取り組めます。
つまり、学習に取りかかるハードルが低いんですね。
さらに、解けない問題が解けるようになれば、自身の成長も感じやすいです。
(たとえば「数的」の問題が解けた瞬間って嬉しいですよね。)
その結果、論文にはあまり手をつけず、教養対策のみに終始してしまう受験生がたくさんいます。
特別区をはじめ、ほとんどの自治体では圧倒的に論文対策の方が重要なんですが…。
受験生自身も論文の大切さを分かりながら、つい後回しにしてしまうんです。
【その2】自分の論文に納得できず、書き上げられないまま放置する
次に、論文を書こうとするものの、書き上げることができないパターンです。
先ほど、論文学習の難しさとして「自己採点の難しさ」を挙げました。
論文学習を始めたころ、多くの受験生はとても不安な気持ちに襲われます。
「自分の書いた文章って、なんかすごく幼稚な気がする…」
「どこをどう直していけば良い答案になるのか見当もつかない…」
参考書や問題集を見れば模範解答は載っていますが、自分の書いた論文の良し悪しは分かりません。
そして、自信がもてず、一本の論文を最後まで書き上げる(結論まで書く)ことができません。
ただ、公務員試験の論文は、「序論―本論―結論」の3段構成でできています。
結論まで書き上げないことには、論文力はアップしていきません。
本当は「自説を最後まで書き上げる」練習こそ大事なんです。
ところが、多くの受験生は書き続けることに耐えられず、模範解答を読んだり写したりして勉強を終わりにしてしまいます。
それでは「なんとなく分かった」状態になるだけで、本番で書けるようにはなりません。
【その3】「論文ネタ」を集めたり「模範解答」を覚えたりするだけで満足する
「書くことが無いから書けない。だから、論文ネタを集めよう。」
「自分で良い論文を書けないなら、模範解答を覚えてしまえばいいのでは?」
こんなふうに考える受験生もまた多いです。
たしかに論文を書くためには、ある程度の「インプット」が必要です。
良い論文ネタや模範解答を自分の知識としてストックすれば、論文は書きやすくなるでしょう。
ただ、ここで注意しておきたいのは、
✓論文ネタや模範解答を知った上で、自分で書く訓練が最重要である
ということです。
ネット上には、「論文ネタや模範解答を丸暗記すればOK」という意見もありますが、これは危険です。
というのも、丸暗記型の論文対策には大きな3つのリスクがあるから。
①本当に丸暗記しようとすると、かなり時間がかかる
②ちょっと出題の仕方をひねられると丸暗記では対応できない
③論文対策が面接対策にうまくリンクしていかない
特に③のリスクを見落としている人が多いです。
実は、模範解答を丸暗記するだけの勉強で、運よく論文試験を切り抜ける人はたくさんいます。
(2次試験の面接に比べて、1次試験の論文ではあまり人数を絞らない自治体もたくさんあります。)
ただ、
模範解答を丸暗記してきた人と、
「自分の論文」を書く訓練を積み上げてきた人とでは、
いざ面接対策に進んだときに取返しのつかない程の差がついています。
✓「自分の論文」を書く=自己PRや志望動機を自分の言葉で表現する訓練
ですから、「自分の論文」を書いてきた人は、面接対策を始める頃には自分の言葉で面接回答する準備がばっちりできています。
一方で、模範解答を丸暗記してきた人はどうでしょうか?
借り物の自己PRや志望動機、希望自治体についての知識しかもっていないので、「自分の言葉」で回答することができません。
「他には?」「具体的には?」と深掘り質問されると、もう答えられない。
それで焦って、今度は「面接模範回答集」を暗記し始めてしまう人もいます…。
(その暗記にも、ものすごく時間がかかります…。)
丸暗記のみの論文対策って、一見効率的なようで、実はとても非効率なんです。
この記事を読んでいるあなたには、こんな間違った勉強の仕方は避けてほしいと思います。
【つまり】「自分の論文」を書くことから逃げると失敗する
教養試験対策に没頭したり、模範解答を写したり、丸暗記で乗り切ろうとしたり…。
これらのうまくいかない勉強法には共通点があります。
✓「自分の論文」を書くことから逃げている
この1点です。
とはいえ、では具体的にどう勉強すればいいのでしょうか。
次項では、論文が苦手な人でも「自分の論文」を書ける”3ステップ勉強法”を紹介します。
2.論文がツラいあなたを救う勉強法3ステップ
もしあなたが、論文に苦手意識が強いなら、次の3ステップ勉強法を試してみてください。
【ステップ1】良い論文を写経・音読する
【ステップ2】「ヒントあり」で自分の論文を書き上げる
【ステップ3】他人に論文を見てもらう→書き直し→覚えこみ
一見、途中まで「丸暗記」型の勉強に見えますが、実際には大きく異なります。
その点も含め、以下に1つずつ解説していきますね!
【ステップ1】良い論文を写経・音読する
良い論文を書くためには、論文の「中身」を事前にもっておく必要があります。
「中身」とは、たとえば次のようなものです。
✓論文テーマに基礎知識
✓希望自治体や他自治体の事例
✓あなた自身の経験や思い(が文章化されたもの)
✓公務員としての心構えや決意(が文章化されたもの)
あなたがもし、これら論文の「中身」をまったく持っていなければ書けなくて当然です。
とはいえ、これらを1個ずつ覚えていくのは膨大な時間がかかります。
そこで、オススメしたいのが、良い論文(参考書の模範解答など)を写したり、音読したりすること。
「良い論文=分かりやすい論文」なので、初学者でもスラスラ読めるはず。
たくさん読んで「なるほど」と思ううちに、自分自身も論文に書かれていた「中身」を覚えられます。
ただ、その際に「黙読」では、なかなか頭に入っていきません。
写したり、音読したりすることで、効率的に論文の「中身」をゲットできます。
また、この2つの勉強(写経・音読)はどちらもやった方がいいです。
というのも、それぞれにメリットがあるからです。
✓写経のメリット→本番に向けて鉛筆で書き慣れることができる
✓音読のメリット→スマホのボイスメモ等で録音すれば、スキマ時間に「耳勉強」もできる
PCに慣れた私たちは、鉛筆をもつこと自体かなり少なくなっています。
結果、実は書くスピードがかなり落ちている人が多いんです。
写経で普段から書く訓練をしておきましょう。
また、忙しい人ほど音読を録音して、あとで聴き直す「耳勉強」を活用してほしいです。
慣れれば通勤・通学中や家事をしながらでも論文学習ができます。
気軽にサクッと短時間で論文学習をすることが可能になるんです!
【ステップ2】「ヒントあり」で自分の論文を書き上げる
ステップ1の方法で数テーマ学習しておくと、自分で論文を書くハードルはグッと下がります。
というのも、先に紹介した論文の「中身」や毎回使われるような定番表現が体に染みこんでくる(あなた自身の知識になり、使えるようになる)からですね。
しかし、ここで学習を終わりにしてはいけません。
(もしくは、一字一句の模範解答を丸覚えしようとしてもいけません!)
ここからついに、自身の考えや思いを加えて「自分の論文」を書き始めるのです。
ただ、そうはいっても、最初のうちは手が止まることが多いでしょう。
そこで、次の工夫をしてみてください。
✓ステップ1で学習したテーマに近い(もしくは同じ)テーマで書く
✓本当に困ったら、参考書やネット検索をヒントにして書き続ける
ここでは、とりあえず「自分の論文」を書き上げることを大事にしたいです。
ですから、大学の「持ち込み可」の試験のように、ヒントありで良いので書き続けましょう。
その結果、模範解答の写しになってしまうような箇所があってもOKです。
(ただ丸写しになっては意味がないので、「ヒントを見られるのは1回5分」とか、「丸写しは連続2文まで」というようなマイルールを設定すると良いでしょう。)
どんなに稚拙に見える文章でも、書き上げたことに大きな価値があります。
そして、次のステップで論文力をグッと伸ばすことができます。
【ステップ3】他人に論文を見てもらう→書き直し→覚えこみ
くり返しになりますが、論文学習は自己採点が難しいです。
それを解消する方法はただ1つ、他人に論文を読んでもらうことです。
公務員試験を知っている人がベストですが、家族や友人に見てもらうことも価値があります。
なぜなら、「良い論文=(誰が読んでも)分かりやすい論文」だからです。
なので「読んでみて分かりづらい場所を教えてほしい。」とお願いしてみるといいですね。
そして、問題があった箇所は書き直し、また読んでもらいましょう。
このくり返しで、あなただけの合格答案が出来上がっていきます。
(良い答案ができあがったら、これは覚えこんでもOKです。自分の答案なので覚えやすく、また他テーマの論文が出題されても応用が効きやすいです。)
ただ、合格に近づくためにはやはり、公務員試験論文を熟知した人に添削してもらうのが一番です。
また、試験まで時間が限られていたり、何回も見てもらいたかったりする場合、家族や友人には頼みづらいということもあるでしょう。
そんな時は、ASK公務員の「オンライン添削」を活用してください。
✓全国どこからでもオンライン受講可能
✓プロ講師が論文力アップに直結する指導
✓論文添削だけでなく今後の学習指針も明示
万全の指導体制で、あなたの本気を全力サポートします!
3.まとめ
本記事のまとめです。
| ✓論文が苦手な人にありがちな3つの状況 ①教養試験の勉強ばかりする ②自分の論文に納得できず、書き上げられないまま放置する ③「論文ネタ」を集めたり「模範解答」を覚えたりするだけで満足する |
つまり、「自分の論文」を書くことから逃げると失敗する、ということでした。
そして、論文に苦手意識がある人でも「自分の論文」を書き上げる勉強法をご紹介しました。
| ✓論文が苦手な人もできる3ステップ勉強法 【ステップ1】良い論文を写経・音読する 【ステップ2】「ヒントあり」で自分の論文を書き上げる 【ステップ3】他人に論文を見てもらう→書き直し→覚えこみ |
ステップ3で論文を見てもらうことで、論文力は飛躍的に向上します。
ASK公務員の「オンライン添削」なら、全国どこからでもプロの指導を受けることができます!
以上です。
本記事を読んだあなたが「自分の論文」を書き上げ、夢を叶えられるよう応援しています。
それではまた!
公務員試験の論文対策を独学で対策するには?注意点や頻出テーマも紹介
以前に比べ、論文試験も分かりやすい教材が多く出版されていたり、公務員試験合格のためのノウハウがあちこちに転がったりしているため独学でも対策しやすくなっています。
「論文対策はしなくても大丈夫」という人もいますが、それは絶対に避けるべきです。その人は大丈夫だったかもしれませんが、一般的に対策をせずに合格ラインに届く人はごく少数だからです。
とはいえ、実際には論文対策を独学で進めることに不安を抱く方が結構多いのはないでしょうか?他の科目と違い、暗記で対応できる部分が少ないイメージがあるからだと思われます。
また、論文はセンスがないと書けないという方もいらっしゃいます。
しかし、十分に対策することで、センスは関係なく合格点を取ることはできます(論文でライバルと差をつけるのは難しいので、最低ラインを目指せれば良いです)。
とはいえ、間違った方向で勉強を進めていてもなかなか合格ラインに到達することはできません。
本記事では、独学で論文対策を検討している方へ向け、どのように学習を進めていけば良いのかを解説します。
1.公務員試験の論文対策を独学で進める方法
まずは具体的な学習方法についてお伝えします。
1-1.論文の書き方の「型」を理解する
公務員試験の論文対策では、まずは論文の書き方の型を覚えることが重要です。
例えば、「結論→問題の背景→問題の解決策→解決策の普及策」のような答案の大まかな流れや、禁則処理などの原稿用紙の使い方のルールなどです。
論文にはいくつかの作成ルールが存在し、そうしたルールが守られていない答案は減点の対象となってしまうので必ず覚えるようにしましょう。
また、型を理解することで以下のようなメリットがあります。
- 論理の流れがわかりやすい答案を書きやすくなる
- 毎回同じ型にはめて書くので、書くのが速くなる
型がしっかりできていないと、まともな論文を書くのは非常に難しいです。
ですので、最初に論文の型をしっかり学んでください。
公務員試験の論文の型を知るには以下のテキストがおすすめです。
本書は公務員試験の論文の型がまとめられており、テーマごとに紹介されている型に当てはめて書いていくことで良い答案が作成する練習ができます。また、良質な模範解答が載っているので、インプットにも最適です。
1-2.論文で問われるテーマについての知識をインプットする
公務員試験の論文の型を覚えたら、論文で問われるテーマに関する知識をつけていきましょう。
ただし、論文試験のテーマの範囲は決まっているわけではないので、全てのテーマについての知識をつけようとしてもキリがありません。他の科目の勉強もあるので、そこまで論文対策に時間を割くことも難しいでしょう。
そのため、ある程度対策するテーマの数を絞ることが効率的です。
頻出と言われるテーマを抑え、余裕があれば過去問などを参考に、できるだけ対応できるテーマを増やしていけばよいでしょう。
テーマに関する知識をインプットするには本書がおすすめです。
こちらは毎年改定されており、公務員試験の論文の最新テーマに関する知識を身につけることができます。ただし、量が膨大なので、優先順位をつけて必要な部分をピックアップして使っていきましょう。
また、公務員試験の論文で問われやすいテーマの一部をご紹介しますので参考にしてみてください。
1-3.論文試験の模範解答をたくさん読みこむ
論文試験対策として、実際にとにかく論文をたくさん書くことが必要だと思われるかもしれません。
実際に書くことよりも大切ですが、模範解答の読み込みも非常に重要です(もちろん質の良い模範解答でなければいけませんが)。
「よい答案」が何か分からず、漠然と論文を書いてもなかなか上達しません。頭の中にインプットされた情報がないのにアウトプットをすることは難しいでしょう。
質の良い模範解答をたくさん読み込むことで、自然と論文の基本となる型、テーマに関する知識が頭の中に入ってきます。インプットすることで良質なアウトプットができるのです。
論文試験も他の科目と同様、ある程度の暗記が重要になってくるということは頭に入れておきましょう。
そしてこうした点が、論文対策は独学でも対応できる点でもあるのです。
1-4.模試で実際に論文を書いて第三者に採点してもらう
模範解答を読み込むことが重要とはいえ、一度も書かないのは流石におすすめしません。
ですので、できる限り模試を受けたりすることで、論文を書いて予備校など専門の講師から添削をしてもらいましょう。
第三者に見てもらうことで、誤字脱字や主語と述語のねじれ、テーマに対する解答とずれている、といった自分では気がつかない部分について指摘をもらうことができるので精度を上げることができます。
なお、ASK公務員の「オンライン添削」では論文の添削および合格のためのポイントを詳しくお伝えしていますので、書いた答案を送付いただくことで添削可能です。詳しくはこちらのページをご覧ください。
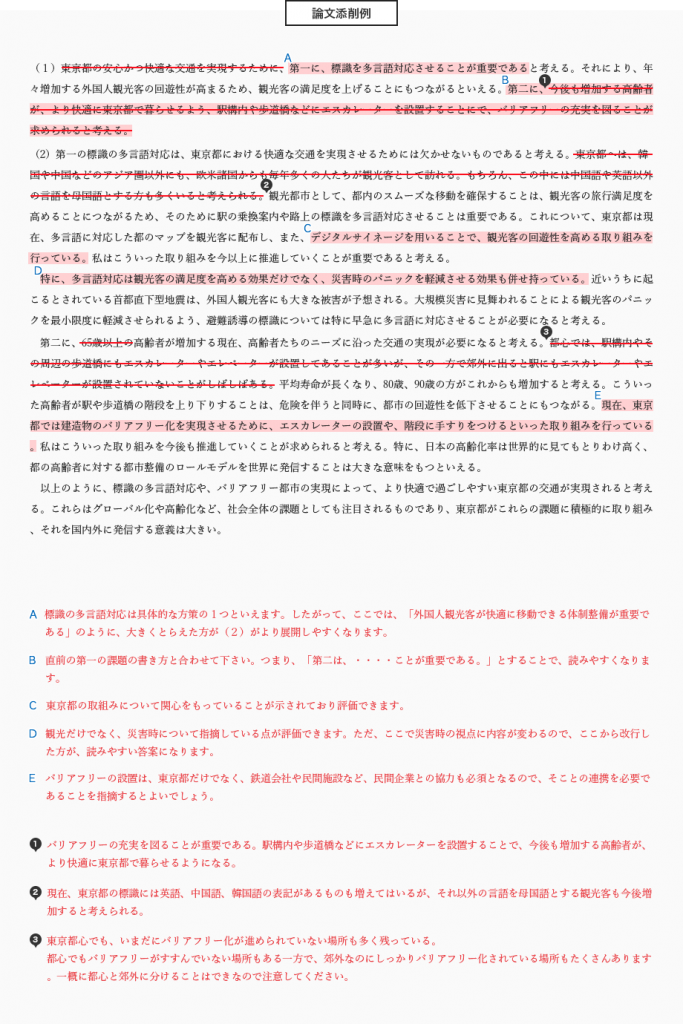
1-5.論文対策はいつから始めるべきか?
予備校に通っていればカリキュラムがあるので自然に論文対策を開始することができます。
一方、独学の場合はどうしても他の筆記試験の科目の勉強に追われ論文の勉強が疎かになりがちです。とはいえ論文は合否を左右する重要な科目なので手を抜くことができません。
「じゃあ、いつから勉強を始めればいいの?」ということですが、だいたい本試験の3か月前くらいから始めていくとよいでしょう。
とはいえ、これは公務員試験全般に言えることですが、全ての人に当てはまる基準というものは存在しません。
例えば、
- 論文の配点が大きい自治体を受験する場合
- 文章を書くことが非常に苦手な人
- 前年受験したけど論文で失敗した人
こうした人は年明けなど早い時期から対策をする必要があります。
ASK公務員にも直前期に慌てて問い合わせをする方がいますが、一朝一夕では論文作成に必要な力を身につけるのは難しいのが実情です。
2.公務員試験の論文の勉強をする際に意識すること
論文対策は漫然と勉強していてもなかなか良い答案を書くことができません。ここでは論文たいセクではどういうことを意識して勉強すればいいかお伝えします。
2-1.知識の豊富さよりもわかりやすい答案を書けることを目指す
公務員試験の論文では政策などの知識の豊富さが大切だと思われる方がいますが、正直それほど大切ではありません。
もちろんある程度の知識がないと論文は書けませんが、受験生の知識はたかが知れていますので、そこで実力に大きな差がつくわけではありません。
本当に大切なのは、論理の流れがわかりやすい論文を書く力のことです。
わかりやすい論文とは、読み手側が「ん?これはいったいどういう意味だろう?」「この原因からなぜこういった問題が起こると言えるの?」というような疑問を抱かずにすらすらと読める論文を書けるかどうかということです。
わかりやすい論文を書くためには、上記で紹介したような本で型を覚えたり模範解答を読み込むことも重要ですが、主観ではわかりやすいかどうかという基準が分からないので、やはり書いた答案を添削してもらうことが重要になります。
2-2.なるべく速く丁寧な字を書けるようにする
採点官は人間ですから、論文の字が汚いと心象を悪くし、得点が低くなる恐れがあるので、字は丁寧に書かなければいけません。
「自分は字が汚いし…」と言われる方も多いのですが、大切なのは綺麗な字を書くのはなく丁寧な字を書くことです。字があまりうまくなくても、丁寧に書いた字は読めば分かります。
なので、普段殴り書きのような字を書いている人は、論文対策では丁寧に書くことを練習もしてみてくださ。
その一方で、試験には制限時間があるので、ゆっくり字を書く余裕はありません。そのため、普段からなるべく速く丁寧な字を書けるように練習することも必要になります。
特に最近ではスマホやパソコンをメインに使用しているので、字をそもそも書く機会もほとんどないかと思います。だからこそ、こうした基本が非常に重要になるのです。
速く丁寧な字を書く力はすぐに身につくものではないので、普段字を書くたびに意識するとよいでしょう。
速く丁寧な字を書けるようにすることで、試験本番で答案構成にかけられる時間も長くなるので、一石二鳥です。
3.まとめ
公務員試験の論文を独学で対策する方法についてお話させていただきました。
再度言いますが、公務員試験の論文は独学で合格点を取れるようになることは可能です。
ただ、努力の方向性を間違えないように(闇雲に様々なテーマに関する知識をインプットするなど)していきましょう。
▼参考記事
[blogcard url=”https://ask-koumuin.com/ronbun/”]
公務員試験の論文の書き方について講師が詳しく解説します
公務員試験では、択一試験、面接試験のほか、論文試験(※)が実施されることも多くあります。択一試験では、社会人として求められる知識と事務処理能力を主に判断し、面接試験では受験生の人柄や採用側との相性を判断しています。
論文試験では受験生の何を判断しているのか?どんなテーマが出題されているのか?
このようなことが気になる受験生も多いことかと思います。
面接重視の傾向にある公務員試験ですが、論文試験も重要な試験のひとつです。
論文はセンスだ、対策をしてもあまり意味がないということをよく聞きますが、それは間違いでありしっかりと対策をしなければ合格することはできません。
ここでは公務員試験の論文試験ついて知っておくべきことや対策について詳細に説明しています。
これから対策を始める方、そして始めてみたけれども不安に感じている方は参考としていただき、少しでも合格に近づいてください。
※自治体等によって論文試験、作文試験など呼び方が若干異なります。ここでは、専門論文試験(法律・経済などの専門的知識を問う試験)ではなく、受験生の見識や関心などを問ういわゆる教養記述試験をまとめて「論文試験」とします。
1 論文試験の評価要素と重要性
論文試験は国家一般職や地方自治体の行政職等で実施されることがあり、特に都道府県庁でよく出題されています。北は北海道から南は沖縄県まで、多くの都道府県で採用されています。
論文試験の「評価要素」は各受験先の受験案内などに「論文試験の内容」として掲載されていることがあります。
たとえば以下のように記載されています。
「社会事象への関心、思考力、論理性等を問います。」
(平成28年特別区Ⅰ類 採用案内)「文章による表現力、課題に関する理解力などについての短い論文による筆記試験」
(平成28年国家一般職(大卒程度) 受験案内)「思考力、創造力、論理力、柔軟性等についての筆記試験」
(平成27年度神奈川県職員採用試験のお知らせ)「見識(社会事象に対する基礎的知識や、論理的思考力、企画提案力、文章作成力などを問います。)」
(平成27年大阪府職員採用試験案内)
自治体等で表現の違いや要素の若干の違いはありますが、評価要素は主に以下のとおりとなっています。
①論理性、論理的思考力
②理解力
③社会への関心度
④表現力
さらに、市町村を含めた地方自治体では、受験生の主体性や積極性といった人物的な面も評価されているといわれています。
近年、公務員試験では特に面接重視と言われていますが、実は論文試験も決して手を抜けない重要な試験です。
論文試験は1次試験に実施されたり2次試験に実施されたりと様々で、しかも配点を公表していない自治体がほとんどです。
その中で配点を公表している神奈川県をみてみましょう。
■神奈川県行政
・第1次試験
教養試験(択一式40題)・・・配点100点、専門試験(択一式40題)・・・配点100点・第2次試験
論文試験(記述式)・・・配点100点
グループワーク・・・配点50点
第1回個別面接(15分)・・・配点50点、 第2回個別面接(30分)・・・配点200点
※最終合格者は、第2次試験の結果のみで決定。
(引用元「平成27年度神奈川県職員採用試験のお知らせ」)
神奈川県は第1次試験の結果はリセットされる方式なので、論文が実施される第2次試験の配点をみてみましょう。
さすが面接重視の自治体なだけあり、面接の配点が非常に高くなっています。
しかし、第2次試験400点満点中、論文は100点を占めます。グループワークや第1回個別面接の2倍の配点です。
グループワークは当日のメンバーに若干影響されたり練習する機会が少ないこと、第1回個別面接は面接時間が短いためあまり点数に差がつかないことを考慮すると、しっかり対策をすれば点数が必ず伸びる論文でできるだけ点数を稼ぐべきといえるでしょう。
グループワークで失敗しても、論文で十分に挽回できる配点になっています。
では別の視点から愛知県の採用案内をみてみます。
■愛知県行政Ⅱ
(専門試験に代え、論文試験や面接試験などにおいてその能力を評価する試験種。)・第1次試験・・・教養試験30点(択一式50題)、論文試験15点
・第2次試験・・・口述試験(面接)55点
※各試験科目の成績が一定基準に達しない場合、他の試験科目の成績にかかわらず不合格となる(つまり科目ごとの足切りあり)。
(引用元「平成27年度愛知県受験案内」)
こちらも面接重視で、配点が半分を超えています。しかし、その面接の前にまず第1次試験を突破しなければなりません。
たしかに論文試験の配点は15点ということで全体の配点比率は低くなっています。
しかし、教養試験の択一式は50題で30点の配点です。専門試験の択一と異なり、教養試験は範囲が膨大で細かい知識や超難問が出題されることもあります。
つまり、合格者の中ではさほど差がつかない傾向があります。各種模試等の傾向を見てみても、教養択一については25点前後に合格者が多く分布していることが多くなっています。
このように考えると、択一式ではあまり差がつきません。
したがって、論文で少しでも差をつける必要が出てきます。少なくとも、論点違いの論文や表現力に乏しい論文では1次合格も難しくなるでしょう。
さらに、足切りがあることにも注意が必要です。
どの自治体も面接の配点は高くなっていると思いますが、択一試験よりも論文試験を重視する傾向もあるようです。また、上述のように択一試験では合格者が同じ点数付近にかたまって分布しているため、論文試験でしっかりと得点する必要も生じてきます。
論文試験だからといって手をぬかない、これが最終合格への重要事項になります。
2 論文試験の過去の出題テーマと特徴
論文試験の過去の出題を知ることは、論文対策の重要なポイントになります。
近年は、各自治体が過去2、3年分の出題例をホームページ上に掲載していることも多いので、興味のある自治体について過去問を掲載していないか確認してみましょう。
2−1 地方自治体の論文テーマと特徴
以下、ランダムに各自治体で公表している論文出題テーマを紹介します(引用元は全て自治体ホームページから)。
それぞれコメントを入れています。自分とは全く関係ない自治体であっても、コメントから地方自治体の論文テーマの特徴が見えてくると思いますので参考にしてみてください。
北海道(大卒程度、一般行政・教育行政・警察行政) H26年度
「北海道新幹線の開業は、本州との移動時間の大幅な短縮に伴う道内外との人的・物的交流の活発化など、地域再生の起爆剤として期待されている。
今後、開業効果を広く波及させるため、解決すべき課題について述べるとともに、道の財政状況を踏まえ、道が優先して取り組むべきことについて、あなたの考えを述べなさい。」
仙台市(大卒程度事務) H26年度
「地域の魅力を発信していくことの必要性と、その際に行政が果たすべき役割について、あなたの考えを論じなさい。」
川崎市(大卒程度、行政事務) H27年度
「川崎市では、急速に変化する近年の社会経済状況などに対応する「新たな総合計画」の策定に向けて検討を進めています。
総合計画とは、これからの川崎市の目指すべき方向やそのための取組内容を明らかにする、10年間程度のまちづくりの計画であり、川崎市の将来に向けた道しるべと言えるものです。
そこで、「10年後の川崎市をどのようなまちにするべきか」という川崎市の将来像について、現在の社会情勢や今後の社会環境の変化などを踏まえながら、あなたの考えを述べてください。」
愛知県(大卒程度) H27年度
「グローバル化が進展する中、愛知県が世界中の人材や資本を取り込んで飛躍するためには、何が必要と考えるか。」
H26年度
「非正規雇用の拡大について考えるところを述べよ。」
大阪市(事務行政) H27年度
「通常、公務と民間企業の違いとして、経済的利益の追求と社会的問題の解決の違いであるといわれることが多い。しかしながら、現在では、NPO*1、ソーシャルビジネス、CSV*2など社会的問題の解決に公務以外が取り組むことも多く、その重要性も増している。公務として取り組む課題と業務の範囲はどのように考えるべきか。
その状況下であなたが公務を目指す理由について、あなた自身がこれまで学んできたこととこれまでの経験などを踏まえて述べてください。
*1 NPO(Nonprofit Organization):非営利団体
*2 CSV(Created shared value) :共有価値の創造」
論文対策をしっかりしていた受験生は高度な論文に仕上げられたであろうが、そうでなくても面接対策として必須の「公務」について論文試験の段階で追求できていれば乗り切れたのではないか。
福岡市(大卒程度) H27年度
「福岡市は,政令指定都市となって今年で43年目を迎えます。現在,政令指定都市は20都市ありますが,福岡市が政令指定都市であることのメリットと,そのメリットを生かし,今後,福岡市はどのように発展していくべきか,あなたの考えを述べなさい。」
2−2 特別区の論文テーマと特徴
例年1万人以上の申込者がいる特別区では、論文が合格の重要なカギになり、論文に泣く受験生も毎年多数発生しています。
特別区では論文の配点は公表していないので生の受験生情報になりますが、択一試験の素点がギリギリだったにもかかわらず、1次合格しさらに最終合格は2桁代の上位合格だった!とか、択一の素点はかなり高かったのに1次不合格だった!など、教養論文がいかに重要かを伝えるエピソードが毎年寄せられています。
特別区の出題テーマについては、親切にも全試験種の過去問を3年分掲載してくれていますので、是非確認してみましょう。
まず、特別区Ⅰ類採用試験では、
「論文の課題は2題あり、このうち1題を選択してください。」
となっています。
当日選択できるのは精神的に良いですね。
平成27年は次の2題が出題されました。
1
「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければなりません。特別区ではすでに、自治体事務のアウトソーシングとして、公共施設の指定管理などを行っていますが、施設の利用者が増大する一方で、様々な課題も見られます。
このような現況を踏まえ、自治体事務のアウトソーシングについて、特別区の職員としてどのように取り組むべきか、あなたの考えを論じなさい。」2
「人々の働き方に関する意識や環境が社会経済構造の変化に必ずしも適応しきれず、仕事と生活が両立しにくいという現実に直面しています。誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て、介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう仕事と生活の調和が求められています。
このような現況を踏まえ、ワークライフバランスの実現に向け、特別区の職員としてどのように取り組むべきか、あなたの考えを論じなさい。」
(引用元:「特別区人事委員会 採用試験情報」HP)
以上の課題をみて、簡単に感じましたか?難しく感じましたか?
テーマ自体は地方自治体でよく出題されオーソドックスなもので、難易度は2題とも標準レベルだと考えられます。
特に課題2は受験生にとってかなり書きやすいテーマでした。少なくとも受験生ならそう感じられる程度に準備しておく必要があります。
最近の傾向として、「特別区の職員として」の取り組みを論じる形式になっています。一般論ではなく、受験生自身が特別区の職員になったことを想定した書き方が必要になります。ここで受験生の主体性や積極性を伺うことができます。
また、「特別区」という行政主体ができることをしっかり理解していることが必要になります。
以下、各課題についてどのようなことを軸に書けばよかったのかをコメントしますので参考にしてみてください。
課題1について
地方自治体の受験生であれば誰しも「自治体事務のアウトソーシングが進められている」という現状は知っておく必要があります。
では、なぜアウトソーシングが進められているのか、どんなメリットがあるのでしょう。
「住民ニーズ」というキーワードに触れて簡単に論じておくべきでしょう。
↓
しかし、民間事業者に依頼したことで様々な問題も生じます。経費削減からくるデメリット、情報番組やネット上でも話題になったTSUTAYA図書館の選書問題など、自分の頭の中の情報を引き出し整理していきましょう。
↓
そして、このようなアウトソーシングから生じる課題を行政がどのように関わって解決していくのかを、後半にしっかりと論じていくというテーマでした。
「指定管理者制度」用語自体を論文中に使用しなくても問題ありません。しかし、これらの知識があるかないかでは、論文に大きな差がつきます。このような知識は面接にも大いに役立ちます。
課題2について
受験生でワークライフバランスという言葉を知らない人はいないでしょう。特別区に限らず多くの公務員受験生が準備をしているテーマともいえます。
しかし、ワークライフバランスのテーマは比較的書きやすく、イロイロと書きたくなってとりとめもない論文になるリスクがあります。締まりのある論文にまとめることがポイントになります。
ワークライフバランスが重要なのは分かっていても、現実問題としてその実現は難しい、それはなぜなのか。子育てや介護のために、特に女性は仕事を諦めざるをえない現状など。たくさんの問題があります。
↓
これらの問題に対する行政の対応を後半でしっかりと論じていきましょう。
前半でたくさんの課題・現状が出てくると思いますが、その中から論点を自分でいくつかに「絞る」という決断が必要になります。
※課題1より2を選択した受験生の方が多かったかもしれません。
しかし、書きやすいテーマほど注意してほしいところ。知識面ではあまり差がつかないからこそ、その知識の深さや文章構成力、表現力の実力差が如実に表れてしまうのです。
特別区の論文対策については特別区の論文試験の基本から対策までトコトン解説の記事も併せてご覧ください。
2−3 国家一般職の論文テーマと特徴
国家一般職(行政区分)は1次試験に「一般論文試験」が課されます。「文章による表現力、課題に関する理解力などについての短い論文による筆記試験」という内容になっています。
配点は全体の1/9と低めです。行政区分では専門択一が4/9と非常に高くなっているので、一般職についてはやはり専門科目の対策が1番といえるでしょう。
しかし、公表されている合格者の決定方法には、「基準点に達しない試験種目が一つでもある受験者は、他の試験種目の成績にかかわらず不合格となります。」とあります(いわゆる足切り)。しかも、記述式試験の基準点は個別に定めるとしかないので、油断は禁物です。
国家一般職の論文と特徴として、以前はグラフや表などの資料解釈を通じて論じていく問題が続いていました。ただ最近は形式が変わり、抜粋分などの文章を読んで設問(1)(2)に答えるという形式になってきました。
今後、どちらの形式でも出題される可能性が高いので、前者にも慣れておくとよいでしょう。
平成25年の採用試験では以下の課題が出題されました。
「以下は平成 24 年版科学技術白書の抜粋である。これに関し(1)及び(2)の問いに答えなさい。
『東日本大震災は,自然の猛威を前に,我々が築いてきた現代文明がいともたやすく破壊され,多くの尊い命が失われてしまう現実を,さらには,これまで日常生活を豊かにしてくれていた科学技術の限界や,社会・経済システムの脆弱さを我々に突き付けた。(ア)今回の震災が科学技術の 各分野や科学技術政策に投げかけた課題は深く,重い。しかしながら,「社会の新たな問題はさらなる科学技術の発展によって解決される」と思っている国民の割合が,震災を契機に低下したものの依然として6割を超えていることからも明らかなように,国民の科学技術の発展に対する期待は,震災を経た今もなお強い。想定を大きく超えた今回の地震及び津波に対しては,従来の科学技術の成果が必ずしも国民の期待に応えられなかった面もあるが,一方で,地震に際して,緊急地震速報により東北新幹線が緊急停止し被害拡大を防いだこと,耐震補強技術により甚大な被害を免れた橋梁等の例もあったことなど,科学技術が被害拡大防止に貢献した面もある。
また,戦後から,河川堤防等の治山治水事業の進展やアメダス,気象衛星等の導入などにより,我が国が自然災害に耐え得る強靱さを備えてきたこともま た事実である。
今後,政府は,震災が投げかけた様々な課題に真摯に対応していくことを通じて,国民からの 信頼の回復に努めるとともに,我が国が震災からの復興茜再生を果たし,将来に向けて持続的に発展していくために,その原動力となり得るのが科学技術であるということにも思いを致しなが ら,(イ)社会の要請に応えた科学技術の振興に努めていかなければならない。』(1) 下線部(ア)について,東日本大震災が科学技術の各分野や科学技術政策に投げかけた課題は何か。 あなたの考えを具体例を交えながら述べなさい。
(2) 下線部(イ)について,(1)で述べた課題を解決し,今後,社会の要請に応えた科学技術を振興して いくためには,どのような取組が必要となるか。あなたの考えを述べなさい。」
(引用元:「国家公務員試験採用情報NAVI」)
科学技術白書の抜粋分からの出題でした。当然、白書は読んでいなくても問題ありません。国家一般職では、(1)→(2)と誘導してくれるので、高校の数学の問題のようにある程度は書きやすい形式にはなっています。
そこで内容面で合否が決まっていくことになります。
この論文では、政府が、東日本大震災の課題と対策を、科学技術の側面から論じることが求められています。つまり国が取るべき防災対策を論じることになるでしょう。
防災対策の論点はオーソドックスなテーマで準備している受験生がほとんどだと思いますが、今回は基礎自治体としての取組みではなく、国としての取組みだということを注意して論じてほしいと思います。
ところで震災が投げかけた科学技術面の課題と問われて、悩んでしまう受験生もいるかもしれません。そんなときは、震災時の混乱を思い出してみて下さい。
通信状態はどうだったでしょうか。被災地はもちろん被災地から遠く離れた地域であっても、携帯がつながらず安否確認がとれないなど、不安を感じた人も多かったと思います。携帯はつながらないけど、SNSはつながる!ということで、SNSの情報共有が盛んに行われましたね。
このように情報通信の面から取組みを論じることができます。
教養論文では、専門的な知識は必要ありません。一見難しい内容に思えても、実は自分が経験したことを素材にしていることがほとんどです。
予備校では専門的な用語も含めて論文対策を行うこともありますが、細かい知識に溺れず、まずは社会的に大きな話題になったもの(娯楽系の情報番組などでも取り上げられるような誰もが知っている話題)について、何が問題でそれについて行政がどのように取組みできるのかを、その都度意識しておくとよいでしょう。
3 公務員試験の論文の書き方・対策について
さて、ここでは具体的にどのようにして論文を書いていけばよいかを確認していきます。
公務員試験の論文では名文を書くことは求められていません。合格レベルの論文にさえ仕上げられればよいのです。
その合格レベルの論文は、
(1)形式面
(2)内容面
の側面から判断することができます。
(1)形式面
①誤字・脱字がないこと
各自治体等でどのように評価しているかは不明ですが、たとえば誤字・脱字1字につき1点減点する方式や、誤字・脱字の量によって「表現力」を低く評価するといった方式がとられます。
合格スレスレの答案が、誤字・脱字で不合格答案に格下げになるのは非常に残念です。これは「見直し」をすることで防止できます。
②指定された字数を守っていること
たいていの論文試験では、1000字以上1500字以内や、1200字程度という指定があります。指定されたルールを必ず守る必要があります。これを守らないと大きく減点されることでしょう。
「何字程度」という指定があった場合は、一般的には8割以上、できれば9割以上の字数で書いてほしいと思います。1200字程度という指定なら、960字以上(できれば1080字以上)になります(このあたりは厳密に考える必要はありませんが・・・。)
この位書かないと、出題者の意図を理解して答えていない不十分な答案ということにもなり、内容面でも評価が低くなります。
③主語・述語が対応していること
受験生の答案をみていて「わかりにくい・意味が伝わらない」と思う答案は、たいてい主語・述語が対応していません。例えば、以下の例をご覧ください。
いかがでしょうか?
述語が「実現していきたい」という意志を表しているのに、主語は意志をもたない「目標は」になっています。本来であれば次のように書くべきです。
もしくは
「私の目標は、〇〇市の職員として住民ニーズをしっかり把握し、そのニーズを実現していくことである。」
1文が短ければ、書いている途中で主語と述語が対応していないことに気がつくことが多いのですが、1文が長いと(文章を書き慣れている人ですら)主語と述語が対応しなくなってくることがあります。
したがって、1文の文字数はほどほどにするということを意識しましょう。
形式面については以上のほか、④原稿用紙を正しく使えていること、⑤句読点を適切な位置に打っていること、⑥文体(ですます調/である調)が一貫していることなどが挙げられます。
形式面で減点されることにならないように、文章を書く際には常に意識しておきましょう。
(2)内容面
①出題意図を正しく理解していること
論文を書く出発点であり、論文の肝ともいえるのが「出題者の意図を理解すること」になります。
出題者は、「こういうことを書いてほしい」という意図をもって問題文を作成しますので、それとは的外れなことを書いてしまっては、どんなに素晴らしい内容であったとしても、あっというまに不合格答案となってしまいます。
問題文が長文だと一見難しく感じるかもしれませんが、むしろ長文の方がヒントがたくさん隠されていることが多いです。問題文を大まかに読むのではなく、細分化して分析することで、出題者の意図がみえてきます。
あわてずに問題文を何度も読み返してみましょう。
②根拠・理由を説明していること
論文は作文とは異なります。小学生の時にたくさん書かされた作文は、①自分の経験や体験→②それに対する感想を書いていくものです。
しかし論文は、①事実や意見に対して→②自分の判断を理由を付けて主張すること、をいいます。
読み手を説得できるような根拠・理由を、客観的に述べていく必要があります。その根拠・理由の深さが、内容の深さにつながります。その根拠・理由の深さは、テーマに対して日ごろから情報を得たり、考えたり、議論をすることで深まります。
そういう意味で、論文対策やはり必要といえるでしょう。
③主体性・積極性がみられること
特に基礎自治体の論文では、「〇〇市の今後の取組み」について論じさせることが多くなっています。
答案の前半で、“〇〇市の現状→問題点”を指摘することは当然必要なのですが、自治体の現状についてしっかりと調べているが故に、前半を長々と書いてしまい、結局それに対する取組みが浅い論文になってしまうことがよくあります。ひどい場合は、市政の批判が論文の中心となってしまうこともあります。
そこで、書き始める前に全体の構成をしっかりと考えることが重要なポイントになります。
現状・問題点に対する「取組み」を後半で深く書き上げることで、受験者の行政職員としての主体性や積極性といった前向きな態度をみることができるのです。
4 まとめ〜文章を書くのが得意な人、苦手な人〜
文章を書くことが得意な人ほど論文対策を後回しにし、場合によってはぶつけ本番ということがあります。
しかし、制限時間内に字数を守って合格答案を書くことは、思っているほど簡単なことではありません。特に最近は、鉛筆やペンで直に長文を書くことがほとんどないので、頭で思ったことを最後まで書ききれないということがあります。
したがって、文章を書くことが得意な人でもある程度の論文対策(準備)は必要といえます。
一方、文章を書くことが苦手な人でも論文対策をしていれば十分に合格答案を書くことができます。なぜなら、公務員試験の論文のテーマはある程度しぼられるからです。さらに、書き方もある程度の型があるとも言えます。
地方自治体の論文対策は、そのまま面接対策にも役立ちます。
択一試験の勉強が最優先にしつつ、論文対策もできるだけ早い時期から少しずつ始めていくと、精神的に余裕をもって試験日を迎えられることでしょう。

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ