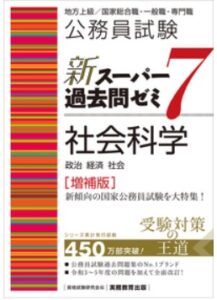1.はじめに
公務員試験の直前期となると、焦ってくる心理状況と、覚えなくてはならないことが多いことが重なって学習が手につかなくなってきませんか。
本記事は、3点に絞って、直前期の筆記試験対策に関して、何をどうすべきかをアドバイスします。
なお、試験対策の筆記は、SPIなどの民間筆記試験型ではなく、公務員特有の教養試験を想定しています(民間筆記試験型については、こちらの記事を確認ください)。
2.直前期対策方法①ー暗記科目を重視して学習を
直前期対策の1点目は、暗記科目を重視するということです。暗記科目とは、社会科学に分類される政治・経済・社会・時事、人文科学に分類される日本史・世界史・地理・倫理(思想)、自然科学に分類される物理・地学・生物・化学を指します。
なぜ、暗記科目を重視した方が良いかというと、それは、そもそも暗記という行為自体、直前期にやったほうが試験まで覚えていられるからです。皆さんの中にも、一夜漬けで中高の定期考査を乗り切った方がいると思います。そのように、直前期に、短期記憶力に賭けて頭に叩き込むわけですね。
なお、直前期ですから科目は絞りましょう。何の科目を学習した方が良いかについては、「自身の学習経験」と「出題数」の掛け合わせで考えていきます。
「自身の学習経験」とは、中高時代や公務員試験で学習してきたことを意味します。やはり、学習してきた場合は飲み込みが早いので、素早い暗記が期待できるからです。
そして、「出題数」はそのままですが、自身の受験する公務員試験種をきちんと調べて、その出題数の多寡によって決めるわけです。
ただ、その科目に絞って学習するにしても、知識系の出題数の7割程度に届かない場合は、「科目の重さ」に注目して、学習する科目を追加しましょう。「科目の重さ」とは、大学受験における暗記量(参考書の分厚さ)を比べて薄いものを実施するということです。
科目系統ごとにその点をお伝えしていきましょう。
社会科学は、暗記項目が少ない順が社会→経済→政治です。社会は時事も絡み、時事の出題数はいろいろな試験種で多いので、社会は学習すると良いでしょう。なお、経済は確かに政治よりは覚える量は少ないですが、グラフだったり、やや数学的な思考力が問われるもので苦手意識がある方は、暗記量にとらわれず、政治をしても良いでしょう。
人文科学の暗記項目が少ない順は、倫理(思想)→地理→日本史→世界史です。この順が負担としても小さくなるでしょう。
自然科学の暗記項目が少ない順は、地学→生物→物理→化学です。ただ、物理は計算などが多く苦手意識の強い方は化学と入れ替えて考えても良いかなと思います。
以上の考えを、実際に、具体例で当てはめてみましょう。
例えば、警視庁一類を受験するとします。50%以上とれれば筆記は通過できるといわれる試験です。教養科目の出題数は、政治4問、経済2問、社会3問、日本史2問、世界史2問、地理2問、思想1問、国語3問、英語2問、物理1問、地学1問、生物1問、化学1問です。全部で25問あるわけですね。
そして、受験する方が、高校時代文系、社会科目が日本史と政治経済(公共)、理科系科目が生物を主に学習してきたとします。
この場合、政治・経済・社会・日本史・生物はした方が良いことになります。学習経験をしているからです。
ただ、これですと、先の出題数25問中12問ですから、7割以上にあたる18問まで増やしていきましょう。まず、国語の出題数が多いので、国語を選びます(これで15問となります)。
では、残り3問のために、考慮するのが「科目の重さ」です。
具体的には、世界史と地理が同じ2問となっていますが、地理となります。そして、残り1問は、思想か、理科系で最も軽い地学かは、参考書を読んで好みで選びましょう。
つまり、地理+思想か、地理+地学で3問ということです。
こうなれば、25問中18問の学習をしていることになります。集中している分、正答率は期待できるでしょうが、仮に7割正解しているとすると、18問×0.7=12.6問です。残りの7問中1問くらいは勘であたるでしょうから13問正解としましょう。
これに、数的・文章の習得(25問中15問正答の6割)と合わせれば50問中28問正答で56%となり、50%を超えられます。
以上は、警視庁Ⅰ類試験を例に考えましたが、何を暗記学習して悩む方は、「自身の学習経験」と「出題数」から考えて、重視して学習する暗記科目を絞ってみてください。ただ、それでは、合格に届きそうな問題数に至らないときは、「科目の重さ」を考慮して学習科目を判断しましょう。
究進塾では、個別相談で学習計画もつくっていますので、悩む方はご利用ください。
3.直前期対策方法②ー継続的な知能科目学習に励む!
直前期対策の2点目は、継続的な知能科目学習に励むことです。
知能科目とは、数的推理・判断推理・資料解釈・文章理解を指します。
これらの科目は、解法のコツというか、知らないと短時間には解けないものというのが数多くあります。そのため、学習の初期や中期はそれに触れている方が多いと思います。直前期は、これを忘れないように、コツコツ学習することが望ましいです。
言い換えると、たくさんの時間をかけなくても良いので、1日数問ずつコツコツ解きましょう。特に、文章理解と資料解釈は、徐々に早く文が読めたり、各選択肢の計算手順が分かるようにもなるので、さぼらず行いましょう。
また、数的推理と判断推理は、出題されやすい単元というのがはっきりしています。こちらの記事にもありますが、この単元の問題から取り掛かると良いでしょう。
4.直前期対策方法③ー模試の有効活用を心がける!!
直前期対策の3点目は、模試の有効活用を心がけることです。
模試の有効活用とは、次の3つです。
第1は、本番を意識して解くということです。これは、解く順番、解けなさそうだったり時間がかかったりする科目・問題は後回しにするなど工夫しながら解くということです。この訓練をすると、実力を得点にしっかり反映できるようになります。
ちなみに、最近は自宅受験できるサービスが多いですが、その場合も、きちんと時間を測ってくださいね。
第2は、復習は全問題やりこむということです。模試は、販売している予備校や会社が、「本試験問題を当てよう!」と思って作っています。したがって、選択肢の一つ一つが本当に分かっているか確認をしたり、本番みたいに取り組んでいたときには時間的に解いていない問題をしっかり解いたりすることで、本番に似た観点が問われたときに功を奏します。また、時事は、なかなか過去問がありません。時事本を読んでいるとどうしても自分が覚えているのか分からなくなりますが、模試を通じて、出会った時事問題を活かしましょう。
第3は、関連分野の復習を即座に行うことです。例えば、模試で日本史の鎌倉時代が出た際に、解けていなかったら、鎌倉時代全体を復習するなどを行うということです。出題をきっかけに広く復習すると大いに知識が定着します。
ちなみに、模試は5回分くらい取り組むと良いでしょう。
5.おわりに
本記事では、公務員試験型(教養)の試験直前にどのように学習をしていくべきかについてアドバイスをしました。
これをまとめると、日々、暗記科目を絞って比重を傾けつつも、知能科目はコツコツと継続して問題に取り組む学習をすることと、模試を受けるときは本番のように解き、模試後は全問復習と関連分野の復習をたっぷり行うことになります。
参考にしていただき、皆さんの学習が進むことを願っています(なお、究進塾では、復習していても中々、問題が解けないなどの悩みに12時間短期集中の数的コースがあります。ご検討ください)。

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ