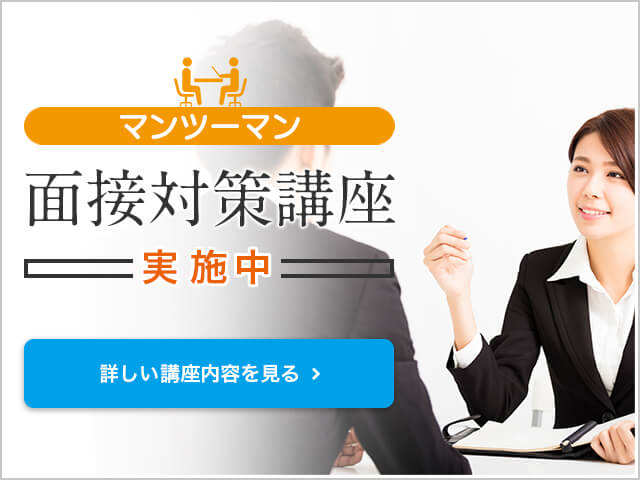公務員試験の面接試験は大きく分けて、個別面接、集団面接、集団討論という3つの形式があります。
個別面接のみ実施される場合が多いですが、市役所や県庁では、個別面接の他に、集団面接や集団討論が実施されることもあります。
集団面接・集団討論はそれぞれどのような方法で行われるのか。また、どのように対策をしていけばいいのか。
今回は、これから試験を迎える方にそれぞれの内容と具体的な対策方法について詳しく解説していきます。
1 集団面接の方法
集団面接は次のような形式で行われます。
②受験生は5〜8人程度
③時間は30〜45分程度
④質問に対しては、端から順番に答えさせたり、挙手制で答えさせたり、ランダムに指名したり、面接官によって様々
⑤面接官に対し受験生が対面して座り、複数の受験生が同時に比較される
人物重視の傾向にある自治体では、筆記試験ではあまり受験生をふるい落とさずに、個別面接・集団討論・集団面接の面接を複数回実施して採用者を決定することが多くなっています。
面接の順番は自治体によりまちまちで、集団討論・集団面接を先に実施するところもあれば、集団面接を最後に行って採用者を最終決定することもあります。この場合、集団面接の面接官には市長や副市長、教育長などの要職が並びます。
2 集団面接のポイントと注意点
集団面接の最大のポイントは、
「他の受験生と直接比較される」ことです。
面接側にとってはとても効率的な面接方法であり、受験生にとっては最もシビアな面接方法といってよいでしょう。
受験生が5〜8名整列すると、受験生が思っている以上に差が出ます。話す内容はもちろん、挨拶やしぐさ、服装、話し方などから、「この子が欲しいな」、という意見は面接官の中でたいてい一致するものです。
なので,個別面接以上に気を引き締めて面接に挑んでください。
では集団面接の具体的なポイントを確認します。
評価項目は個別面接とほぼ同じ
集団面接だからといって個別面接と異なる基準で評価されるわけではありません。
基本的には個別面接と同様の基準で評価されます。自治体により異なりますが、態度・服装、論理性、表現力、協調性、積極性などが主な評価項目になります。
他の受験生の話も聞く
集団面接ならではのポイントです。
一度質問を受けて次の受験生に質問が移っても、「〇〇さんの意見についてはどう思いますか?」と質問が戻ってくる事があります。自分の発言が終わっても安心せずに、他の受験生の話をしっかりと聞いて下さい。その聞いている姿勢も面接官はみていて評価していきます。
質問には簡潔に答える
個別面接以上に注意しなければならないポイントです。
集団面接では、30分程度の時間の中で複数の受験生に質問しなければなりません。1人が長々と話してしまうと他の受験生の面接時間も削ってしまいます。とりとめもなく長く話すような受験生は、面接官が話しを止めることもあります。そうならないようにできるだけ簡潔に答えてください。
面接官がもっと話を聞きたいと思えば必ず「もう少し話してもらえますか?」とか「それは具体的にどういうことですか?」などと問いかけてもらえます。
挙手制での注意点
面接官に「挙手で答えてください」と言われた場合、積極的に手をあげるようにしてください。手を挙げないと発言回数が減り、その分アピールポイントも減ってしまいます。
しかし、毎回1番早く手を挙げる必要はありませんし、気後れする必要もありません。重要なのは答えの中身です。自分の考えがまとまってから挙手するようにしましょう。
どんぐりの背比べではダメ
複数の受験生の中で自分をアピールする必要があります。たとえば集団面接のある回で8人の受験生がいても、みんながぱっとしないどんぐりの背比べのような状態だと、8人全員が不合格となることがあります(逆もあります)。そうならないように、自分が1番だという意識を持って積極的にアピールをしていきましょう。
3 集団面接の具体的な質問事項
集団面接といっても質問される内容は個別面接と変わりません。なので、個別面接の対策をしっかりしておけば安心です。実際にどのような質問がされるのか、いくつか列挙しておきますので参考にして下さい。
《導入・雑談など》
・ この市に来たことはありますか?それはどんなとき?
(小規模な自治体であったり、都心から離れていると聞かれることが多いです)
・ 待合室で何してたの?
(待ち時間が長くなるグループもあるので聞かれることもあります)
・ 休みの日は何しているの?
・ 公務員の予備校には通ったの?
《自治体の施策について》
・ この市に感じる魅力は何ですか?
(王道の質問です)
・ この市の施策で興味をもっているものは何ですか?
(具体的な施策について知っているか?といった形でも質問されます。)
・ この市が財政難にある理由を答えて下さい。
(自治体の大きな課題について聞かれることがあります。)
《受験生自身について》
・ 30秒で志望理由を答えて下さい。
・ 30秒で自己PRをしてください。
(集団面接では30秒や1分など、短い時間で説明させることがよくあります。)
・ 今までで一番辛かったことは何ですか?
・ 今までで一番楽しかったことは何ですか?
・ 職員になったらどんな仕事をしたいですか?
以上のほか様々な質問がされますが、「個別面接と変わらないな」という感想をもつと思います。
集団面接の準備はまず個別面接の準備をすることだと考えて下さいね。
4 集団討論の方法
集団討論は次のような形式で行われます。
②受験生は5〜8人程度
③時間は30〜60分程度
④受験生同士で1つのテーマについて議論する
⑤討論の方法については当日具体的に指示される
集団討論は、当日同じグループになったメンバーで1つのテーマについて議論し、それを面接官が評価していく面接の1つです。
最も注意しなければならないのは、上記⑤です。
討論の方法については、当日採用者側から具体的に指示されます。
たとえば、
・テーマについての結論を必ず出す
・テーマについての結論を出さなくてもよい
・司会などの役は決めないこと
・司会などの役は決めても決めなくてもよい
・議論の前に1人ずつ自分の意見を発表してもらう
・スタートの合図ですぐに議論に入ってよい
など。
指示に反したことをすれば大きく減点されます。
自分は大丈夫でも、他の受験生が指示を守らないこともあります。そのときは必ず指摘してください。指摘しないと、グループ全員が不合格となってしまうおそれもあります。
5 集団討論のポイント
ここでは集団討論のポイントを見ていきましょう。
グループ全体で活気のある討論にすることが必要
集団討論の最大のポイントは、同じグループは運命共同体にある、ということです。
メンバーは採用者側が機械的にもしくは色々な事情を考慮して決めるわけですが、受験者側としてはどんな人たちと一緒になるのか当日まで分かりません。自分がどんなに集団討論が得意で優秀でも、ものすごくコミュニケーション力の劣る受験生と一緒になり足を引っ張られる可能性もあります。
中には集団討論中、思考が暴走してしまう受験生もいます。
そういう困った受験生と一緒になった場合には、議論が円滑にすすむように積極的に進行したり、話しがずれていると感じたら指摘したりするなどしましょう。そうすることで自分の評価(貢献度)もあがりますし、グループ全体のまとまりも出て良い集団討論となります。
集団討論では、グループのメンバーほとんどが合格する場合と、グループのメンバーほとんどが不合格となる場合が実際にあります。自分だけ目立とうとはせずに、あくまでグループ全体で活気ある議論ができるように意識しましょう。
発言しないと不合格になる
グループ全体として活発な議論ができたとしても、討論中の発言が全くなかったり、1、2回しか発言しない受験生を面接官は評価のしようがありません。
たとえば30分の制限時間の討論であれば、5回以上を目標に発言するとよいでしょう。
役割(司会、書記、タイムキーパー)ごとの注意点
面接官から特に指定がなければ、役割を分担するのもよいでしょう(必ずしも司会などをおく必要はありませんが、役割を決めることで円滑に討論が進める事ができます)。
司会は自分の意見も述べながら、他のメンバーの意見を集約し、議論を円滑に進めていく必要があるのでなかなか大変な役になります。しかし、これが成功すると積極性や貢献度などいろいろな面で高く評価されます。模擬討論などで1度司会をやってみて自分が向いていると思ったら、是非やってみるのもよいでしょう。
ただし、司会としての自信がないのに、あえて本番で司会をやってみる、というのは自分の評価を大きく下げるだけでなく、他の受験生の足をひっぱることにもなるので辞めた方が得策です。
書記はメンバーの意見をうまくまとめてメモをしていきます。場合によってはホワイトボードなどが用意されていることがあるので、そこにメモしながら最後の発表で使うのもよいでしょう。こちらも貢献度などの点から評価されます。
しかし、メモをするのに必死になり、自分の意見が言えなくなってしまう可能性もあります。書記だけに専念できるわけではないので注意してください。
タイムキーパーは役割の中では1番やりやすいです。
たとえば、話し合うべき論点が3つにしぼられた場合(論点をしぼったりするのは司会の役目です)、「〇〇分たったので、そろそろ次の論点にうつりませんか?」と促したり、「終了時間まであと〇〇分です。そろそろまとめに入りませんか?」などとメンバーに伝えます。司会や書記と違って負担は少ないので、自分の意見を考え発表する余裕も十分にある点でおすすめです。
6 集団討論の具体的な対策
5〜8人程度のメンバーで1つのテーマについて制限時間内に自由に討論するという形式は、なかなか経験することがないかもしれません。
法学部などでディベートを積極的に行うゼミもありますが、こちらは専門知識をもとに批判、反論、再反論を繰り返す形式であり、公務員試験の集団討論とは若干性質が異なります。
もちろん公務員試験の集団討論でも反論は必要ですが、決して人の意見を否定せずに温和に話し合い1つの結論を共に導いて行くという姿勢を忘れないで下さい。
では実際にどのように準備をしていくのか、具体的な対策です。
①まず、下記のような一般的なテーマについての自分の意見を考えてみましょう。
・ 厳しい財政状況の中で住民が満足するサービス提供について
・ まちおこしをするためには何をしたらよいか
・ 地域の活性化について
・ 公務員のワークライフバランスについて
・ 高齢者や子どもが安全で安心し、いきいきと暮らせるためにはどうするべきか
②つぎに、近年話題になっている社会事情や時事問題についても勉強しておきましょう。
下記のような出題がされていますので、筆記試験の時事対策の延長で知識を入れておきましょう。
・ 外国人観光客の増加に伴い、各地で宿泊施設が不足しており、その対策として政府は民泊の規制緩和について議論を進めているが、住環境の維持、既存宿泊施設の保護等の観点から厳しい規制を求める意見もある。各自治体はどのように対応すべきか、あなたの意見を述べ、討論しなさい。
・ 女性活躍推進法が平成28年4月1日から施行されているが、女性活躍の例として、従来、男性中心の職場であるようなイメージであった建設業などの職場での活躍が見られるようになってきている。今後、女性が活躍する社会にするため、男性中心のように思われていた職場に女性活躍の機会を増やすために、行政としてどのような対応をすべきか、あなたの意見を述べ、討論しなさい。
③上記①・②で勉強したり考えたことはそのまま個別面接にも役立ってくることなので頑張って頭を使って準備して下さい。
しかし、集団討論では様々な個性をもったメンバーと話し合いをする必要があります。
たとえばメンバーの中に誰もリーダーシップをとって討論を進行してくれる人がいなかったということもあります。その場合は、自分が行動していくしかありません。なので、実際に模擬討論などに参加して、自分はどのような役割を果たせるのかを確認しておく必要があります。いろいろなメンバーと実践を積む事で,自分の長所短所が必ず見えてきます。そしてそれが自信につながります。
集団討論では自分の頑張ってきたことも志望動機も聞かれません。それなのに、集団討論で不合格とされてしまうのはとてももったいないことです。なので、本番の前に少なくとも1度は模擬討論をしておくことを強くおすすめします。
7 まとめ
集団面接は個別面接の対策をしっかりしたうえで、集団ならではの緊張感やストレスを軽減できるように練習することが必要です。
そして、集団討論は時事ネタや自治体の政策などを勉強したうえで、集団の中でどのような立ち位置で発言していくか練習することが必要です。
集団面接も集団討論も、実際に複数人で練習しておいた方がよいでしょう。

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ