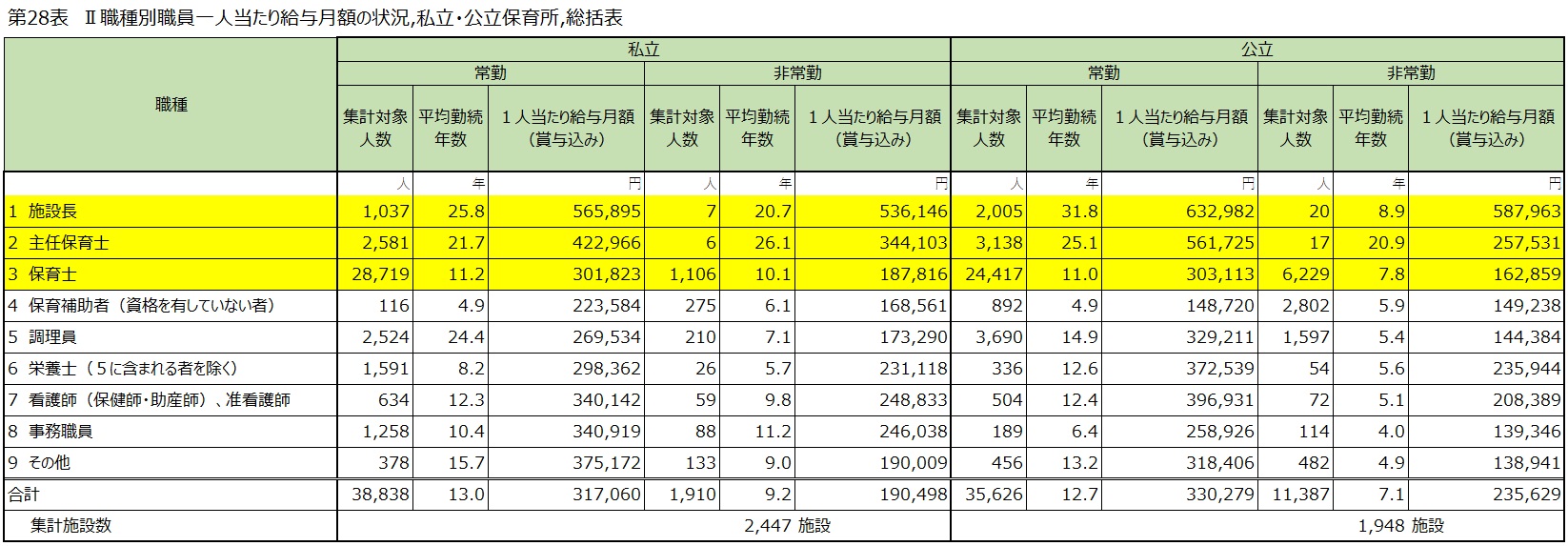公務員の技術職に興味はあるけど、「公務員の技術職にどんな職種があるのか分からない」「公務員の技術職の仕事内容を知りたい」、こんな悩みをお持ちではないでしょうか。
公務員の技術職は、専門分野の知識・技術を仕事に生かしたい人におすすめです。
本記事では、公務員の技術職の種類や仕事内容、年収、試験概要について解説しています。
「公務員の技術職の受験を検討している」「自分が公務員の技術職に向いているのか知りたい」方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.公務員の技術職の種類
公務員の技術職の採用枠を設けているのは、以下の3つです。
①国家公務員(総合職)
②国家公務員(一般職)
③地方公務員 |
公務員の技術職の種類は多数あります。
参考に国家公務員(一般職)の職種(試験区分)9つを以下に示します。
・デジタル・電気・電子
・機械
・土木
・建築
・物理
・化学
・農学
・農業農村工学
・林学 |
国家公務員(総合職)や地方公務員では、職種の呼び名や種類が異なります。
参考に東京都(1類B)の職種(試験区分)を以下に示します。
・技術職:土木、建築、機械、電気
・専門的な職種:環境検査、林業、畜産、水産、造園、心理、衛生監視、栄養士、獣医、薬剤A・B |
東京都の場合、「技術職」のほかに「専門的な職種」という分類が設けられています。
別の地域では、東京都では専門的な職種に含まれている職種が技術職に分類されていることもあります。
まずは自治体の採用情報を確認し、どんな職種があるのか確認することをおすすめします。
希望の職種がない場合は、別の自治体では採用枠が設けられている可能性もあるため、色々な自治体の採用情報を確認してみてください。
2.公務員の技術職の仕事内容
公務員の技術職のうち、主な職種の仕事内容についてご紹介します。
ここでは、地方公務員の仕事内容についてご説明します。
公務員の技術職「土木」の仕事内容
「土木」の仕事内容は、主にインフラ整備に関わる業務です。
道路や鉄道、公園など生活資本の整備と管理、上下水道やダム、河川などの水資源の管理・保全などに携わります。市街地再開発・土地区画整理事業の実施、都市計画の策定などの業務に携わることもあります。
(参考)東京都の主な配属先
・本庁(建設局・都市整備局・水道局など)
・建設事務所
・市街地整備事務所 など |
公務員の技術職「建築」の仕事内容
「建築」の仕事内容は、主に都市計画やまちづくり、公共住宅に関わる業務です。
まちづくりや住宅政策など都市整備に関する企画、公共住宅の建設計画・設計監督などに携わります。建築基準法に基づく指導、公営住宅の運営、自治体保有の建築物の整備などの業務に携わる場合もあります。
(参考)東京都の主な配属先
・本庁(都市整備局・財務局など)
・建築指導事務所 など |
公務員の技術職「機械」の仕事内容
「機械」の仕事内容は、主に機械設備の維持・管理に関わる業務です。
上下水道施設や鉄道などの機械設備の維持・管理や、道路や河川、公園などの機械設備の建設などに携わります。公共建築物の空調設備や給排水設備、浄水場、ダムなどの施設の管理・保全などの業務に携わる場合もあります。
(参考)東京都の主な配属先
・本庁(交通局・水道局・下水道局など)
・車両検修場
・浄水場
・水運用センター
・水再生センター など |
公務員の技術職「電気・電子」の仕事内容
「電気・電子」の仕事内容は、主に電気設備の維持・管理に関わる業務です。
上下水道施設や港湾、空港などの電気設備の維持・管理、道路や河川、公園などの電気設備の施工などに携わります。公共建築物の受電整備や監視整備、浄水場、発電所、ダムなどの施設の管理・保全などの業務に携わる場合もあります。
(参考)東京都の主な配属先
・本庁(交通局・水道局・下水道局など)
・地下鉄電気管理所
・浄水場
・水運用センター
・水再生センター など |
公務員の技術職「化学・環境・衛生」の仕事内容
「化学・環境・衛生」の仕事内容は、主に大気や水質など生活環境に関わる業務です。
大気環境保全施策の企画・実施、工場排水や生活排水、産業廃棄物に関する規制・指導、水源河川や給水栓の水質検査などに携わります。地球温暖化対策、再生可能エネルギーの普及、リサイクルの推進などの業務に携わる場合もあります。
(参考)東京都の主な配属先
・本庁(環境局・水道局・下水道局など)
・浄水場
・水質センター
・水再生センター など |
公務員の技術職「農学」の仕事内容
「農学」の仕事内容は、主に農業の普及・振興に関わる業務です。
農業者への技術指導や新規就農者の確保・育成、地元産の農産物のPRなどに携わります。試験研究機関での調査研究、農業大学校での教育指導などの業務に携わる場合もあります。
(参考)神奈川県の主な配属先
・農業技術センター(本所、各地区事務所)
・かながわ農業アカデミー
・横浜川崎地区農政事務所
・地域県政総合センター
・農政課
・農業振興課 など |
公務員の技術職「林学」の仕事内容
「林学」の仕事内容は、主に森林の保全や林業の振興に関わる業務です。
森林計画の策定、森林の育成・保護、林業の経営指導などに携わります。このほか、山地防災、自然公園、市街地の緑化に係る施策の企画、生物多様性の保全に関する施策の企画・推進などの業務に携わる場合も行います。
(参考)東京都の主な配属先
・本庁(産業労働局など)
・森林事務所
・水源管理事務所 など |
3.公務員の技術職の年収
国家公務員と地方公務員の年収(概算)を以下に示します。
|
平均給与月額(a) |
期末・勤勉手当の
平均支給額(b) |
年収概算
(a×12+b) |
| 国家公務員 |
404,015円 |
約1,311,600円 |
約6,159,780円 |
| 地方公務員(東京都) |
453,549円 |
1,889,761円 |
7,332,349円 |
(表:公的機関発表の令和5年度分のデータをもとに作成)
※平均給与月額:国家公務員は行政職俸給表(一)、地方公務員は一般行政職の区分における平均給与月額を示す。
(参考:koumu_jittai.pdf (jinji.go.jp))
(参考:r05_bonus_dec.pdf (cas.go.jp))
(参考:r05_bonus_jun.pdf (cas.go.jp))
(参考:「都職員の給与の状況」の概要|東京都 (tokyo.lg.jp))
(参考:冬季の特別給の支給 |東京都 (tokyo.lg.jp))
(参考:夏季の特別給の支給|東京都 (tokyo.lg.jp))
国家公務員の年収は約620万円、地方公務員の年収は約730万円です。
給与月額や期末・勤勉手当の支給額は、自治体や年齢、役職などにより異なります。
より詳しい情報が知りたい場合は、それぞれの自治体の給与情報を確認してみてください。
4.公務員の技術職の試験概要
受験申込から採用までの基本的な流れは、技術職と行政職でほぼ変わりません。
行政職の試験と大きく異なる点は、筆記試験で基礎能力試験(教養試験)のほかに、専門試験があることです。選択と記述の問題があります。
受験資格には、年齢制限が設けられており、対象年齢は自治体によって異なります。
2023年度受験を例にすると、国家公務員(一般職、大卒程度)は1993年4月2日以降に生まれた人、地方公務員(東京都、1類B)は1994年4月2日以降に生まれた人が対象です。
職種によっては、特定の資格や免許が必要な場合もあるため、一度自治体の採用情報を確認することをおすすめします。
5.公務員の技術職のメリット・デメリット
公務員の技術職のメリット・デメリットをご紹介します。
公務員の技術職のメリット
・専門分野の知識・技術を仕事に生かせる
・現場で経験を積むことでスキルアップができる
・退職後も専門的な知識・技術を生かせる |
公務員の技術職最大のメリットは、学生時代に学んだ専門分野の知識・技術を仕事に生かせることです。
興味・関心が高い分野の仕事に携わることができるため、モチベーションを保ちやすく、専門家として頼りにされることも多いため、やりがいを持つことができます。
また、現場での実務経験を積むことにより、実践的なスキルを身につけることができるため、成長を感じられ、さらなるやる気アップにつながります。
さらに、退職後も専門分野の知識・技術は強みになります。専門スキルを生かして、関係機関や大学に再就職している事例もあります。
公務員の技術職のデメリット
・人員削減の影響を受けやすい
・専門外の部署への異動は難しい
・事務職に比べて昇進しづらい(出世ポストが限られている) |
技術職は事務職に比べて採用人数が少ないため、退職や人事異動で人員が減少すると、残りの技術職の職員に業務が集中します。
技術職の配属先はほぼ決まっているため、就職後に新しい分野の仕事に挑戦してみたいと思っても、専門外の部署への異動は難しいです。
全ての技術職が出世できないわけではありませんが、一般的に採用人数が少ない技術職は事務職に比べて出世しづらい傾向があります。
6.公務員の技術職が向いている人・向いていない人
「専門分野の知識・技術を生かして人の役に立ちたい」「専門スキルを磨いてプロフェッショナルを目指したい」人は、公務員の技術職が向いています。
このような人は、モチベーションを維持しつつ、やりがいを持って仕事に取り組めるでしょう。
一方、「色々な分野の業務を経験してみたい」「出世欲が強い」人には、公務員の技術職はあまりおすすめできません。
このような人は、仕事内容や人事制度に違和感や不満を抱いてしまうかもしれません。
7.公務員の技術職に関するよくある質問
公務員の技術職に関するよくある質問をまとめてみました。
・公務員の技術職の仕事はきつい?
・公務員の技術職は勝ち組って本当?
・公務員の技術職で狙い目の職種はある?
・公務員の技術職には女性もなれるの?
・公務員技術職はなくなる?将来的に後悔する可能性は? |
公務員の技術職の仕事はきつい?
結論からお話すると、技術職が事務職に比べて仕事がきついということはありません。
しかし、配属先によって超過勤務や休日出勤が多い職場はあります。そのため、仕事量が多く大変だと感じることはあるかもしれません。
仕事をきついと感じるかどうかは、自分の適性と運次第なところがあります。
公務員の技術職は勝ち組って本当?
技術職と事務職を年収と仕事量で比較してみます。
まず年収について、一定の条件を満たした技術職に受給される手当はありますが、多くの技術職の給与表は事務職と同じ行政職の区分に分類されるため、基本給に大きな差はないと考えられます。
次に仕事量について、前項でも説明したとおり、仕事量は配属先によって差があるため、事務職より技術職の方が仕事量が少ないとはいえません。
よって、職種による勝ち負けを考えるよりも、自分の適性に合った職種を選択する方が、充実した公務員人生を送れるのではないでしょうか。
公務員の技術職で狙い目の職種はある?
令和5年度の国家公務員(一般職)の採用状況を以下に示します。
| 試験の区分 |
申込者数(人) |
最終合格者数(人) |
倍率(倍) |
| 行政 |
22,316 |
6,476 |
3.4 |
| デジタル・電気・電子 |
435 |
173 |
2.5 |
| 機械 |
240 |
116 |
2.1 |
| 土木 |
1,045 |
449 |
2.3 |
| 建築 |
163 |
54 |
3.0 |
| 物理 |
284 |
155 |
1.8 |
| 化学 |
491 |
210 |
2.3 |
| 農学 |
756 |
342 |
2.2 |
| 農業農村工学 |
184 |
71 |
2.6 |
| 林学 |
405 |
223 |
1.8 |
(表:「国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)実施状況2023年度」をもとに作成)
(参考:ippann_daisotu_kekka_2023.pdf (jinji.go.jp))
合格者数が多い順に並べると、土木>農学>林学>化学>デジタル・電気・電子>物理>機械>農業農村工学>建築になります。
倍率が低い順に並べると、物理=林学<機械<農学<土木=化学<デジタル・電気・電子<農業農村工学<建築になります。
採用人数や倍率は年により変動がありますが、この結果から考察すると、土木、農学、林学は採用人数が多く、倍率も低いため、狙い目の職種といえます。
逆に、建築や農業農村工学は採用人数が少なく、倍率も高いため、難易度の高い職種であると考えられます。
また、行政職に比べて技術職の倍率が低いことから、行政職より技術職の方が狙い目といえるかもしれません。
公務員の技術職は女性でもなれる?
令和5年4月1日時点の女性国家公務員の採用状況を以下に示します。
|
総数(人) |
うち女性(人) |
女性の割合(%) |
| 国家公務員全体 |
9,063 |
3,504 |
38.7 |
| うち技術系区分 |
1,704 |
464 |
27.2 |
(表:「女性国家公務員の採用状況のフォローアップ結果」をもとに作成)
(参考:20230606_siryou.pdf (cas.go.jp))
技術系区分の女性の割合は27.2%、つまり約4人に1人は女性です。
よって、女性でも技術職の公務員になることは十分可能であるといえます。
国では、技術系区分の女性の割合を令和7年度までに30%にする目標を掲げており、今後さらに女性の採用人数が増えることが予想されます。
公務員の技術職はなくなる?将来的に後悔する可能性は?
この疑問は現職の公務員の間でも以前から囁かれている事柄です。
これから受験を検討している人にとっては、より気になる疑問でしょう。
結論からお話すると、公務員の技術職が早急になくなる可能性は低いと考えられます。
公務員の仕事は職種に関係なく、利益になりにくいものの需要が高い業務や、快適な生活を送る上で欠かせないライフラインに携わる業務が中心です。
そのため、民間企業に仕事が取って代わられる可能性は低いと考えられます。
また、年によって採用人数に差はありますが、毎年採用の募集があり、採用人数が減少している傾向も伺えません。
よって、公務員の技術職が早急になくなる可能性は低いと考えられます。
(参考:https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo/ippan/saiyo_ippan03.html)
8.まとめ
公務員の技術職の種類や仕事内容、年収、試験概要などについてご紹介しました。
公務員の技術職には様々な職種があり、仕事内容は多岐に渡ります。
人員削減の影響を受けやすいことや、専門外の部署への異動が難しいことなどの留意点はありますが、専門分野の知識・技術を生かせることが最大のメリットです。
また、公務員のメリットである経済的な安定、充実した福利厚生を受けられることも魅力の1つです。
「専門分野の知識・技術を生かして人の役に立ちたい」「経済的な安定も手に入れたい」方は、公務員の技術職の受験を検討してみてはいかがでしょうか。

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ