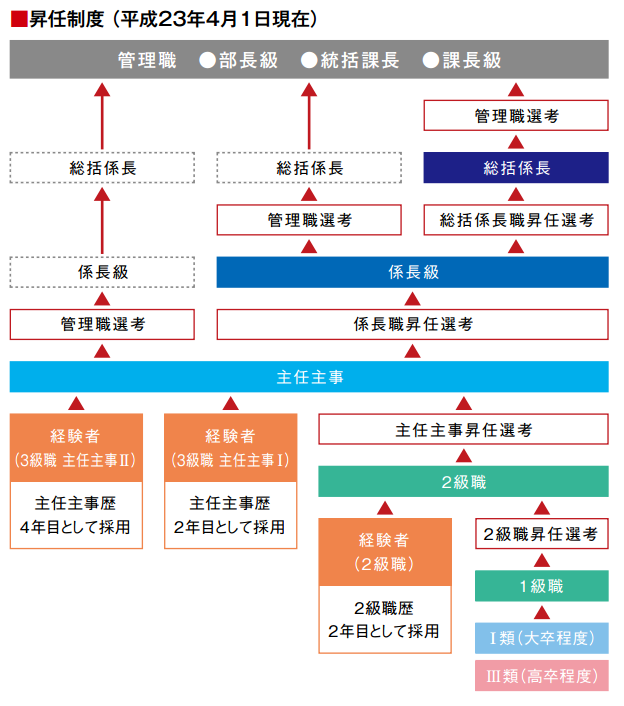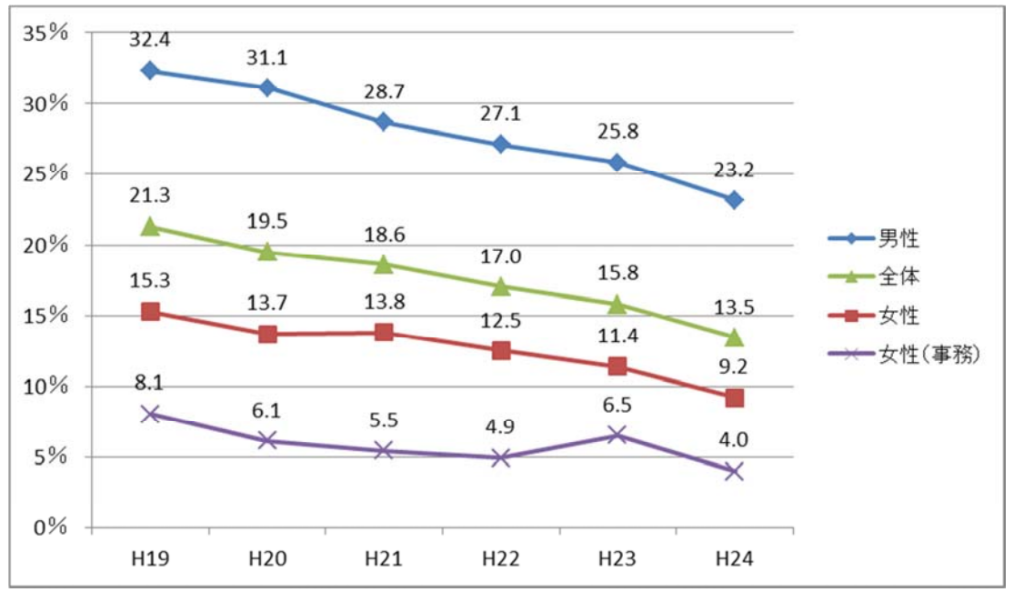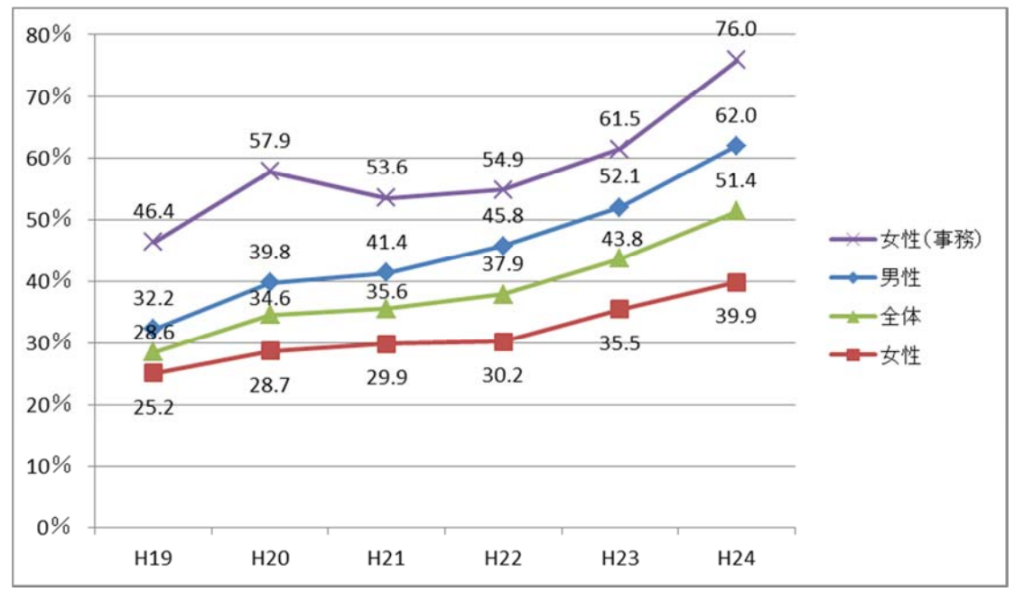公務員は残業もなく定時に帰れる、なんてことをよく聞くかと思いますが、実際のところはどうなのでしょうか?
皆さんの周りで役所に勤めている人がいて、その人は毎日定時だから、やっぱり役所は定時で上がれていいな~と思っている人がいればそれはほんの一部を見ているに過ぎません。
まず、国家総合職は午前様と言われるように、朝まで仕事をして、シャワーだけ浴びに帰ってまた出勤というのが常態化しているようでして、これはあまりに極端な話なのでここでは割愛させていただきます。そしてほとんどの人はそれを知っていると思いますのであえて言うこともないでしょう。
かと言って国家公務員はよく分からないので、私の区役所での経験から書いていきたいと思います。おそらく地方公務員だと大きくは変わらないはずですので参考にしてみてください。
中にはプライベートを充実させたいから定時に帰れる公務員を目指すという人もいるみたいで、一般的に、「公務員=定時上がり」というイメージが浸透しているようです。
では、果たして本当に定時に帰れるかというと、配属先の部署次第としかいいようがありません。
つまり、配属先によって定時に帰れる部署と残業続きの部署に分かれるため、こればっかりは運としかいいようがないわけです。
役所の仕事は大きく分けると、住民対応をする窓口職場と、あまり住民と接することはなく、役所の内部の仕事をしている政策系の職場に分かれます。
窓口職場は住民課や福祉関係、税金関係など、我々一般人が役所に行って立ち寄る場所でありますが、基本的には5時に窓口を閉めるため、比較的早く帰れる傾向にあります(夜間開庁のときは別です)。
もちろん、5時以降に仕事が残っていれば残業をせざるを得ないですし、予算の時期や税金関係の部署であれば確定申告の時期は残業続きとなりますが、そうでないときは多くの職員は比較的早く帰れるかと思います。
ただ、こうした職場が楽かというと話が別で、役所の仕事ってやっぱり楽?の記事でも書きましたが、窓口職場は住民対応がメインとなるので、クレームが多く、メンタルが強くなければやっていけないというつらさがあります。
実際、こうした部署はうつ病など精神を病んでしまい休職してしまう人も多いです。
逆に、政策系の部署は残業が多い傾向にあります。政策系とは、自治体として行う事業や計画を策定したりする部署であり、大きな仕事ができるので花形部署のように思われますが残業が多く、毎日10時ぐらいまで残業ということもザラにあります。
こうした部署は会議が多いため資料作成に追われたり、自治体のトップとの近いところで仕事をすることも多いので、上層部の対応に時間を取られたりするので、どうしても残業が多くなってしまいます。
そして、役所のお偉方との接点が多いので神経も使い、胃が痛くなります(笑)。
こうして見るとそれぞれ一長一短という感じですが、とりあえず「公務員=定時上がり」という発想は捨てたほうがいいでしょう。また、自治体の規模が大きくなればなるほど予算が大きくなり、事業も大規模になってくるため忙しくなるでしょう(もちろん部署によりけりでしょうが)。
ですが、仕事とプライベートを両立している人は結構多いので、忙しいときは集中して仕事に没頭し、そうでないときは定時で上がるようにするなど、メリハリをつければ自分の時間も十分取ることができます。
ということで、公務員は残業があるのかという疑問については、「職場や自治体次第。運の要素が強い」と思っておいてくださいね。では~!

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ