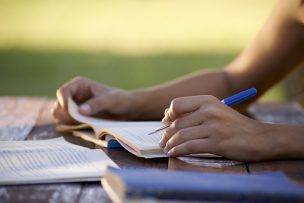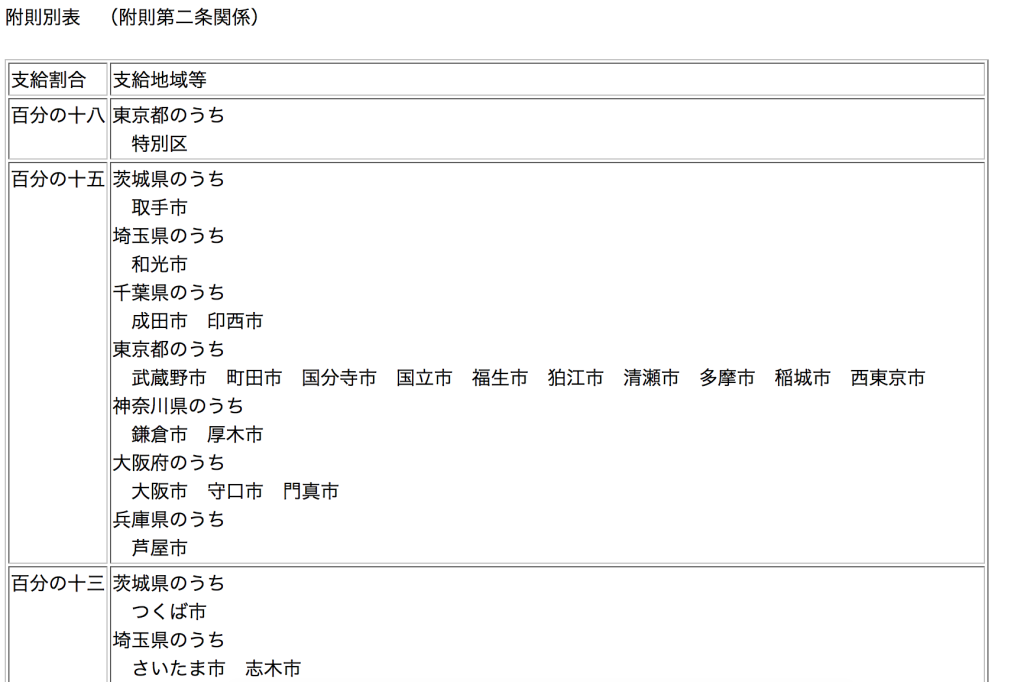裁判所事務官はどんな科目が出題され、どのような対策をすればいいのかわからない受験生も多いのではないのでしょうか?
裁判所事務官についての情報はなかなか手にいれることができず、途方に暮れている人が多いようです。
また、平成27年度の裁判所事務官の試験では、試験名称のみならず、試験科目自体にも若干の変更がありました。
このように裁判所事務官の情報は自ら積極的に情報収集することが求められるため、ここではどこよりも詳細に裁判所事務官の試験科目と対策について書いていますので参考にしてみてください。
1 裁判所職員の試験区分(平成27年度から名称変更)
裁判所職員の試験には大きく、裁判所事務官(総合職・一般職)と家庭調査官補(総合職試験)の試験があります。
平成27年以前から裁判所事務官を受験・検討されている方は、試験名称が若干変更されましたのでご確認ください。以下のように官職が明記されるようになり、非常に分かりやすくなりました。
(旧)総合職試験(院卒者・大卒程度試験,法律・経済区分)
↓
(新)総合職試験(裁判所事務官,院卒者区分・大卒程度区分)(旧)総合職試験(院卒者・大卒程度試験,人間科学区分)
↓
(新)総合職試験(家庭裁判所調査官補,院卒者区分・大卒程度区分)(旧)一般職試験(大卒程度試験)
↓
(新)一般職試験(裁判所事務官,大卒程度区分)
つまり、現行の制度は総合職試験(院卒者区分・大卒程度区分)は裁判所事務官と家庭裁判所調査官補、一般職試験(大卒程度区分)は裁判所事務官として採用されることが明記されるようになったのです。
2 受験資格年齢と試験科目
裁判所事務官の試験では、①総合職か一般職かでの違い、②院卒者区分か大卒区分かでの違いがあります。
また、裁判所事務官と家庭調査官補とのの違いも存在します。つまり、以下のように6種類に分類することができるので、「平成27年度試験案内」をもとにひとつずつ見ていきたいと思います。
(1)総合職試験(裁判所事務官、院卒者区分)
(2)総合職試験(裁判所事務官、大卒程度区分)
(3)総合職試験(家庭裁判所調査官補、院卒者区分)
(4)総合職試験(家庭裁判所調査官補、大卒程度区分)
(5)一般職試験(裁判所事務官、大卒程度区分)
(6)一般職試験(裁判所事務官、高卒程度区分)
2−1 総合職試験(裁判所事務官、院卒者区分)
総合職試験(裁判所事務官)は、院卒者・大卒程度区分ともに3次試験まであります。
院卒者区分と大卒程度区分では、受験資格及び試験科目(1次・基礎能力試験の問題数と、2次・専門記述の出題科目)に違いがあります。
受験資格:30歳未満であって、大学院修了及び修了見込みの方
【1次試験】
①基礎能力試験(択一式)30題(知能27+知識3)
②専門試験(択一式)30題
【必須】憲法7題・民法13題
【選択】刑法10題または経済理論10題(当日、どちらかの科目を選択)
【2次試験】
①専門試験(記述式)4題
【必須】憲法1題・民法1題・刑法1題
【選択】民事訴訟法1題or刑事訴訟法1題
※憲法は、1次試験日に実施されます。
※憲法は六法使用不可、民・刑・訴訟法は当日六法が貸与されその六法のみ使用可。
②政策論文試験(記述式)1題
政策論文試験は与えられた資料等から課題を読み取らせ、それに対する対策を検討させ論述させる試験となっています。詳細は、3−4 政策論文・小論文の対策を参考にしてください。
③個別面接
総合職の個別面接の試験は受験生1人に対し面接官が3人という形式で行われます。
【3次試験】
集団討論および個別面接
集団討論については面接官が3人が見守る中、受験生が複数人である議題に対し討論を行います。
その後、集団討論を踏まえた上で個別面接が行われます。
2−2 総合職試験(裁判所事務官、大卒程度区分)
受験資格: 21歳以上30歳未満の方
【1次試験】
①基礎能力試験(択一式)40題(知能27+知識13)
②専門試験(択一式)30題
【必須】憲法7題・民法13題
【選択】刑法10題または経済理論10題(当日、どちらかの科目を選択)
【2次試験】
①専門試験(記述式)4題
【必須】憲法1題・民法1題・刑法1題
※憲法は、1次試験日に実施されます。
※憲法は六法使用不可、民法・刑法は当日六法が貸与されその六法のみ使用可。
②政策論文試験(記述式)1題
政策論文試験は院卒者程度区分と同様に、与えられた資料等から課題を読み取らせ、それに対する対策を検討させ論述させる試験となっています。詳細は、3−4 政策論文・小論文の対策を参考にしてください。
③個別面接
個別面接の試験は受験生1人に対し面接官が3人という形式で行われます。
【3次試験】
集団討論および個別面接
集団討論については面接官が3人が見守る中、受験生が複数人である議題に対し討論を行います。
その後、集団討論を踏まえた上で個別面接が行われます。
2−3 総合職試験(家庭裁判所調査官補、院卒者区分)
家庭裁判所調査官補はその職業柄、心理学や社会学、教育学等の人間関係科目の出題が多いのですが、試験制度の変更により、民法や刑法を選択することも可能になりました。人間関係科目の科目も1科目は選択する必要はありますが、以前に比べ、非常に法学部生やロースクール生が受験しやすい制度になりました。
受験資格: 30歳未満であって、大学院修了及び修了見込みの方
【1次試験】
①基礎能力試験(択一式)30題(知能27+知識3)
②専門試験(記述式)
次の人間関係諸科学科目および法律学科目 の15科目(15題)のうち選択する3科目(3題)
※試験当日に科目を選択。
※人間関係諸科学科目から少なくとも1科目(1題)を選択。
◼︎人間関係諸科学科目
心理学概論、臨床心理学、社会心理学、社会学概論、現代社会論、社会調査法、社会福祉学概論、社会福祉援助技術、地域福祉論、教育学概論、教育心理学、教育社会学
◼︎法律学科目
憲法、民法、刑法
【2次試験】
①専門試験(記述式)
次の13科目(15題)のうち選択する2科目(2題)
※児童福祉論と高齢者福祉論は同時に選択不可。
※民法のみ2題又は刑法のみ2題を選択不可。
臨床心理学、発達心理学、社会心理学、家族社会学、社会病理学、社会福祉援助技術、児童福祉論or老人福祉論、教育方法学、教育心理学、教育社会学、民法、刑法
②政策論文試験(記述式)1題
政策論文試験は与えられた資料等から課題を読み取らせ、それに対する対策を検討させ論述させる試験。詳細は、3−4 政策論文・小論文の対策を参考にしてください。
③集団討論および個別面接
集団討論が行われた後、それを踏まえた個別面接が実施されます。
2−4 総合職試験(家庭裁判所調査官補、大卒程度区分)
院卒者区分と共通の試験問題で行います。ただし、第1次試験基礎能力試験について解答する問題数が異なります。
受験資格: 21歳以上30歳未満の方
【1次試験】
①基礎能力試験(択一式)40題(知能27+知識13)
②専門試験(記述式)
次の 15科目(15題)のうち選択する3科目(3題)
※試験当日に科目を選択。
※人間関係諸科学科目から少なくとも1科目(1題)を選択。
◼︎人間関係諸科学科目
心理学概論、臨床心理学、社会心理学、 社会学概論、現代社会論、社会調査法、社会福祉学概論、社会福祉援助技術、地域福祉論、教育学概論、教育心理学、教育社会学
◼︎法律学科目
憲法、民法、刑法
【2次試験】
①専門試験(記述式)
次の13科目(15題)のうち選択する2科目(2題)
※児童福祉論と高齢者福祉論は同時に選択不可。
※民法のみ2題又は刑法のみ2題を選択不可。
臨床心理学、発達心理学、社会心理学、家族社会学、社会病理学、社会福祉援助技術、児童福祉論or老人福祉論、教育方法学、教育心理学、教育社会学、民法、刑法
②政策論文試験(記述式)1題
政策論文試験は与えられた資料等から課題を読み取らせ、それに対する対策を検討させ論述させる試験です。詳細は、3−4 政策論文・小論文の対策を参考にしてください。
③集団討論および個別面接
集団討論は面接官3人が見守る中、受験生6人があるテーマについて討論を行います。テーマは一般的な内容(たとえば待機児童問題)についてであり、その後、集団討論を踏まえた上で個別面接が行われます。
個別面接は受験生1人に対し面接官3人という形式で行われます。
2−5 一般職試験(裁判所事務官、大卒程度区分)
一般職試験は、総合職試験と異なり2次試験までとなっています。
総合職試験(裁判所事務官)と重なる試験種目、具体的に択一試験(基礎能力+専門科目)及び専門論文(憲法)では、共通の試験問題が出題されます。
受験資格: 21歳以上30歳未満の方。21歳未満で大学卒業及び卒業見込み、短大等卒業及び卒業見込みの方も受験可。
【1次試験】
①基礎能力試験(択一式)40題(知能27+知識13)
②専門試験(択一式)30題
【必須】憲法7題・民法13題
【選択】刑法10題または経済理論10題(当日、どちらかの科目を選択)
【2次試験】
①論文試験(小論文)1題
※論文試験(小論文)は、1次試験日に実施されます。
②専門試験(記述式)4題
【必須】憲法1題・民法1題・刑法1題
※憲法は、1次試験日に実施されます。
※憲法は六法使用不可、民法・刑法は当日六法が貸与されその六法のみ使用可。
③個別面接
個別面接は受験生1人に対し面接官3人という形式で行われます。
2−6 一般職試験(裁判所事務官、高卒程度区分)
受験資格:高卒見込み及び卒業後2年以内の方 (中学卒業後2年以上5年未満の方も受験可)
【1次試験】
①基礎能力試験(択一式)45題(知能24+知識21)
②作文1題
【2次試験】
個別面接
3 裁判所事務官の試験の特徴とその対策
3−1 専門の択一試験は3科目で受験ができる
裁判所事務官の専門択一は、他の公務員(行政職)試験と異なり特徴があります。裁判所事務官の専門択一は、たった3科目で受験することができます。
憲法・民法が必須科目、これに加えて、刑法か経済原論のどちらか1科目を選択します。
まず、公務員(行政職)試験で必須の行政法が存在しません。行政法が苦手な方には受験しやすい試験といえるでしょう。
また、必須科目の憲法・民法は他の公務員試験と重複するため、試験対策が非常にしやすいといえます。
しかし、「刑法」は裁判所事務官ならではの出題となります。通常、刑法は他の試験では出題されないか、地方上級で2題程度の選択問題となっているため、公務員試験用の勉強として行うことはあまりありません。
ですが、裁判所事務官の仕事が、実際に法廷で働く仕事ですから、業務上必要な知識となってきますので刑法が試験科目に入ってきます。
しかし、多くの公務員(行政職)受験生が、裁判所事務官を併願していることから、「刑法」の変わりに「経済原論」を選択することもできます。経済原論とは、いわゆるミクロ・マクロ経済学のことをいい、公務員(行政職)受験生にとっては主要科目となります。
例年、多くの受験生が、刑法ではなく経済原論を選択し最終合格をしていますので、法学部生でない人は経済原論を選択する方が得策ともいえます。
もっとも、裁判所に入所すると、経済原論は一切使いませんが、刑法の勉強は必須になります(書記官試験の必須科目です)。したがって、合格の先を見据える場合には刑法を選択するのも非常に有効でしょう。
3−2 専門試験の対策方法
裁判所事務官の専門試験は択一試験と記述試験があります。他の公務員試験と異なる部分も多いですが、
3−2−1 択一試験の対策
択一試験では、憲法7題、民法13題、刑法/経済原論10題が出題されます。いずれも、総合職試験と共通の問題になります。
裁判所の試験ということで、「難しそう!」というイメージをもたれる方もいますが、実際には公務員試験でよく出題される基本問題が多く出題されています。また基本をしっかり理解しているかという良問が多くなっています。
したがって、裁判所事務官だからといって特別な対策が必要なわけではなく、公務員試験の過去問集を使って知識を定着させることで十分得点することができます。
■注意点①
法律3科目では、学説問題が出題されることがよくあります。
たとえば平成27年度の憲法の試験では、「公共の福祉」についてA説・B説・C説を紹介したうえで、各説について述べた記述の正誤を問う問題でした。しかし、このテーマも基本中の基本で、過去の裁判所の試験でもほぼ同様の問題が出題されています。したがって、過去問集をしっかり問いていた受験生は簡単に正解にたどりつく内容となっています。
■注意点②
法律3科目では、正誤問題が非常に多くなっています。
正誤問題とは、
「〜に関する次のア〜エの記述の正誤の組合わせとして最も適当なものはどれか」という出題に対して、
「ア正 イ誤 ウ正 エ誤」のように、全ての答えの正誤が合っている選択肢を選ぶ問題です。
これは各記述について確実に分からないと答えが出ない問題であり、難易度が上がります。
したがって、なんとなく過去問集を回すのではなく、基本問題について確実に暗記をしていく丁寧な作業が必要になることを、特に意識してください。
■注意点③
刑法か経済原論のどちらを選択するかは悩ましいところですが、早めにどちらを選択するかを決めましょう。
経済原論がとても難しかった年度もありますが、必ずしも毎年そういうわけではありません。逆に、刑法が難しい年度もあります。
経済原論では、正誤問題が少ない一方で、計算をしてその数値を選択肢から選ぶ問題も半分程あるので、数学が苦手な人にとってはとっつきにくい印象があるかもしれません。
いずれにしても、どちらの科目も一長一短ですし、受験年度によって難易度に大きな波がありますので、早めに選択科目を決定して、選択した以上は迷わずその科目の理解を深めていってください。
なお、ロースクール卒業生や、裁判所事務官・専願の受験生は、迷わず刑法で問題ないでしょう。
3−2−2 記述試験の対策
総合職・一般職の共通問題として、憲法の一行問題が出題されます。一行問題とは、たとえば、「財産権について論じなさい。」といった問題をいいます。
この一行問題では、書き出す論点が決まっています。条文・趣旨・判例・学説等、時間内に読み手に分かりやすくただ書き出すだけです。
対策としては、一行問題用のテキストや問題集をただ暗記し、本番で書けるようにするだけです。
直前期には、各予備校で記述対策講座を単発で売り出していますし、書店には公務員試験用の記述の問題集がいくつか販売されています。
独学で対策される方や予備校だけの対策で不安な方は「公務員試験 論文答案集 専門記述 憲法(早稲田経営出版)」が、論点が比較的よくまとまっており、解答例も使いやすいものとなっているためおすすめです。

公務員試験 論文答案集 専門記述 憲法 〈第2版〉
年明け2月頃から3か月かけて暗記する時間を設けられれば、合格点がつきます。もっとも、暗記したものをいざ実際に書き出してみると、思っている以上に正確に書けないことが多いです。なので、大学の先生や予備校等を利用して、1度添削を受けることも有効な手段です。
一方、総合職では、民法・刑法・訴訟法の出題があります。こちらは、一行問題ではなく、事例問題になっています。問題を読んで、何が論点かを抽出し、それについて知識を吐き出し、自分の見解も書いていくというものなので、難易度がぐっと上がります。
難関私大や国立大学の法学部の定期試験のレベル〜ロースクールの入試のレベルと把握しておくとよいでしょう。(司法試験のような超長文を読解させるものではありません。)
このレベルの市販の問題集はほとんど出版されていませんので、法学部生以外の人は、予備校等のなんらかの利用が必要になるかと思います。また、一行問題以上に、添削してもらうことが重要になります。
大学のゼミの先生や、予備校の講座で添削してもらい、何が足りないのかをしっかりと把握して実力をつけてください。
3−3 教養試験の対策方法
基礎能力試験(択一式)という名称で、総合職では30題(知能27+知識3)、一般職では総合職の30題に知識問題が10題追加して(つまり合計40題)出題されます。
基礎能力試験は、ほとんどの公務員試験で出題され、難易度や範囲も大卒程度の公務員試験とほぼ同じです。したがって、他の公務員試験を併願される人は、裁判所事務官用の対策を特別に設けることは必要ありません。
具体的に、平成27年度裁判所事務官(一般職)の基礎能力の出題数を紹介します。
現代文5題、英文5題、判断推理6題、数的推理10題、資料解釈1題
政治2題、経済2題
法学、日本史、世界史、地理、思想、物理、化学、生物、地学は各1題
(合計40題)
判断推理・数的推理・資料解釈といった数的処理系が17題出題されていますので、ここでかなり差がつくところになります。
もっとも、数的処理系はどの公務員試験でも近年重視されていますので、過去問や模試などを問いて、力をつけていただきたいと思います。
ところで、知識系(法学、日本史、世界史、地理、思想、物理、化学、生物、地学)はたった1題ずつしか出題されていません。
このたった1題のためにどれだけ力を入れるかが問題となります。
私大文系の受験生には、物理や化学、生物、地学を始めから捨ててしまう人がいますが、完全に捨てるのはおすすめしません。
たとえば平成25年度の試験では、化学「気体の性質」、生物「DNA」が出題されています。これらは超頻出分野で、予備校テキストや模試ではメインで扱う分野です。実際の問題はやや細かい知識で得点率は低かったようですが、分野としては是非学習しておきたいものでした。出題年度によっては、頻出分野について非常に簡単な知識問題が出題されています。
また、地学では「地球の構造・火山」といった分野が出題されました。昨年から全国で火山の噴火が問題になり話題となっていたわけですので、出題されてもなんらおかしくないテーマでした。実際の内容も消去法で比較的簡単に答えが出る問題だったようです。
もちろん手に負えない細かい分野が出題されることもよくあります。これは、ほとんどの人が解けませんので差がつきません。
しかし、基本的なテーマが出題されたときに、知識系を完全に捨てた人と、基本分野を万遍なく学習していた人との差が出ます。その結果、合否に影響することになります。
したがって、知識系については、頻出分野(過去問集で傾向が分かります)だけはしっかりとインプットしておくことをおすすめします。
3−4 政策論文・小論文の対策方法
総合職は政策論文、一般職は小論文が出題されます。
◼︎政策論文の対策(裁判所事務官・家庭調査官補共通課題)
政策論文は資料から課題を読み取らせ、その対策を検討させる形式です。(過去問については裁判所のHP掲載されていますが、著作権の都合で掲載されていません。)
平成27年度は「グローバル社会に適応できる人材を育てるための対策」、平成26年度は「家庭裁判所がより国民にとって利用しやすい裁判所となるための方策」といったテーマが出題されました。
政策論文が出題されるようになってまだ数年であり、過去問がほとんどありません。以前は裁判所に関するテーマが出題されていましたが、ネタが切れたのか、平成27年度は一般社会論がテーマでした。
したがって今後も、裁判に関係なく幅広く教養のテーマが出題されると考えられます。
政策論文では、①資料(文献や統計)を時間内によみとり、②そこから課題を抽出し、③自分の意見を書き出します。これらは大学でレポートを書き上げる際に自然に身に付く基本的な力とも言えます。
とりたてて対策は不要ですが、予備校の模試で1度経験しておくことをおすすめします。
◼︎小論文対策
政策論文と異なり資料はついていません。テーマについて自分の意見を述べるものになります。
平成27年度では「いきいきとやりがいを持って働くことができる良好な職場環境を整える上で、あなたが重要と考える要素を検討し、その実現に向けた方策について論じなさい。」という内容が出題されました。
例年テーマは様々ですが、「だれもが書ける」テーマしか出題されません。裁判所に関するテーマは出題されていませんので、安心してください。
また、出題意図をだいたい把握したうえで、日本語として文章が成り立っており、自分の意見を書いている人は合格しているようです。
多くの受験生は特別の対策をしていませんが、文章力に苦手意識がある人は、大学受験の小論文の問題集(資料を読み取るタイプでないもの。)を軽く読んでおくとよいでしょう。
また、日頃からニュースや新聞の社説やコラムを読んで、いま話題になっている社会問題についてのさまざまな意見を収集しておくと、本番に役立ちます。
3−5 面接対策はD評価を取らないようにしよう!
裁判所事務官の試験は人物重視といわれています。それは、裁判所事務官(一般職)の場合、面接の点数(配点比率)が全体の10分の4を占めるからです。
また、面接はA、B、C、Dという評価で、Dは不合格となります。したがって、まずはDをとらないことが絶対条件になります。
ではDをとってしまう人はどんなタイプか紹介します。
①裁判所の仕事を全く理解していない。(行政職とは全く異なる仕事です。)
②公務員試験の併願先のひとつとしか考えていない。(志望動機から、裁判所が本命でないことが分かる。)
③声が小さい。(これはどの試験でも論外。)
④裁判所を利用する国民とコミュニケーションをとれそうにない。
特に④が重要なポイントです。
裁判所には、トラブルをかかえた多くの国民が毎日やってきます。その国民をまず相手にするのが裁判所事務官・書記官になります。そのような国民にいかに親身に手続を説明できるかが重要な仕事になります。
したがって、たとえばプライドが高い人、(法学部生にありがちな)理屈っぽい人、話し方の感じが悪い人、暗い人、調子のよい人は、どんなに成績がよくても、頭の回転が速くても、面接官が裁判所事務官としてのコミュニケーション力が不足しているととらえられてしまいます。
この部分をクリアできた人は、実際の面接でC、Bを確保し最終合格することがほとんどです。
よく裁判所事務官は女性に有利といいますが、これは、受験生全体をみたときに、女性の方が、国民が安心できるコミュニケーションをとれることが多い現れではないかと思います。そういう意味では、公正に判断していると思います。
男性でも、接客業の経験者や、民間企業で渉外経験のある方などは上位で合格しています。(1位合格が男性であることも非常に多いです。)
このような点をふまえて、面接対策をしていくことが重要となります。
(志望動機については【試験種別】絶対に合格するための公務員の志望動機の考え方を参考にしてください)
4 裁判所事務官の難易度は国家一般職・都庁ⅠBとほぼ同じ
裁判所事務官のレベルは、総合職・一般職ともに、筆記試験(教養+専門)のレベルは国家一般職や都庁レベルと考えられます。
また、受験層もほぼ重複しているため、国家一般職や都庁IBの合格者が裁判所事務官に合格することは非常に多いです。
もっとも、裁判所には専門科目の記述式試験がありますので、これらは他の試験種とはなかなか比べられませんが、国家総合職(法律区分)の筆記試験よりはやや易しく、都庁ⅠBと問題のレベルは近いですが、採点が非常に厳しいといえるでしょう。
なお、裁判所事務官(総合職)の場合は、採用人数が非常に少ないという意味で、他の試験に比べ難易度が極めて高いともいえます。しかし、試験問題自体の難易度はそれほど高くありませんので、専門科目の記述対策を十分にできれば合格できる可能性が十分あります。
なお、家庭裁判所調査官補については、試験科目が行政職と異なり特殊のうえ、採用人数も全国で50名程度となっており、こちらは狭き門になっています。しかし、試験科目が特殊ということから受験生の数はしぼられてきます。
したがって、最初から無理だと諦めずに、戦略的に試験対策をすることで合格を勝ち取っていただきたいと思います。
5 まとめ
裁判所事務官(総合職・一般職)について平成27年度の情報を参考に紹介してきましたが、①総合職といえど超難関というわけでないこと、②一般職は、ほかの公務員(行政職)試験と十分に併願できること、を知っていただけたかと思います。
公務員の受験先の1つとして考える人は、重複しない科目(刑法)の手をぬかないこと、裁判所事務官のみを受験される方は、専門科目が少ない分、高得点を狙うこと、を意識して勉強をすすめていってください。
また、必ず受験する年度の「受験案内」を自分の目で確認してください。
大幅な変更の場合は、10月頃〜年内に裁判所のホームページに「お知らせ」が掲載されるかと思います。
特にインターネット上の情報は、最新の情報を掲載していない場合もよくありますので、くれぐれも注意しましょう。

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ