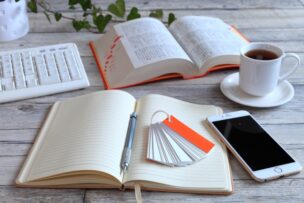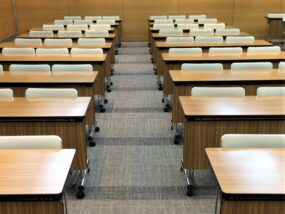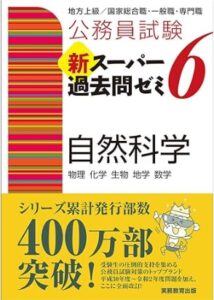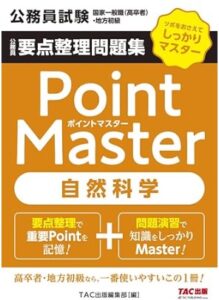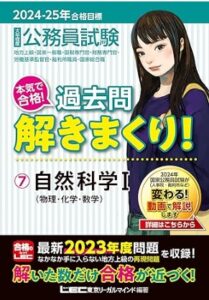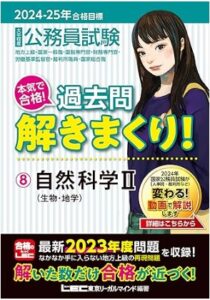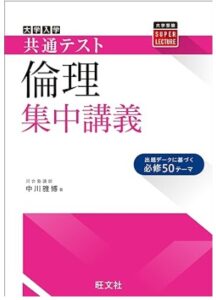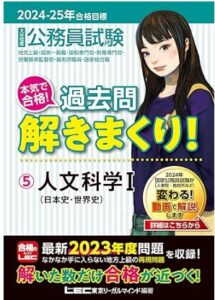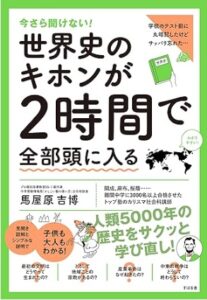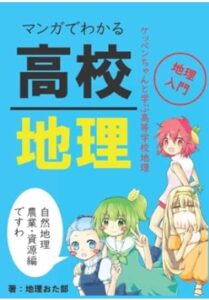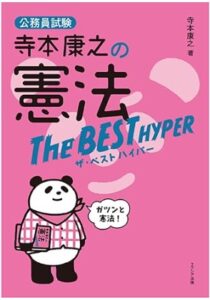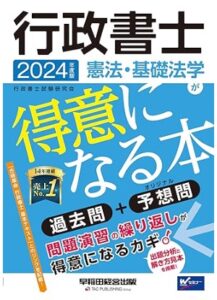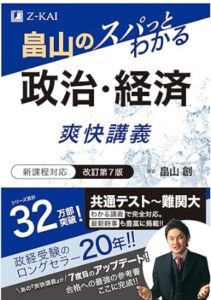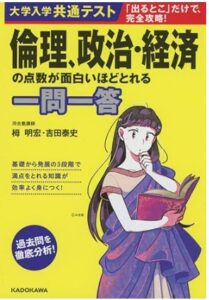「特別区経験者採用は面接が重要らしいけど、どう対策する?」
「特別区面接の特徴や質問例、効果的な勉強法等を知りたい!」
「自分は面接が苦手で…、短期で受けられる講座は無いかな?」
受験生のこんな疑問にお答えする記事です。
特別区経験者採用の二次試験で実施される面接試験。
”最終合格”が決まる重要な試験なので、万全な対策で臨みたいですよね。
そこで本記事では、次のような内容をご紹介します。
✓特別区経験者採用の面接試験の特徴3選
✓特別区経験者採用の面接で聞かれた7つの質問
✓特別区経験者採用の面接に勝つ!5ステップ対策法
面接の攻略ポイントがまとめてサクッと分かる記事になっています。
勉強の合間にぜひ、読んでみてくださいね!
1.特別区経験者採用の面接試験の特徴3選
特別区経験者採用の面接は2次試験で実施されます。
この面接は特別区人事委員会が行うため、「人事委員会面接」または「人事院面接」とも呼ばれます。
この2次試験に合格すると”最終合格”となり、その後に「区面接」があります。
「区面接」はほとんどの受験生が合格します(100%ではないことには注意が必要ですが…)。
そのため、「人事委員会面接」こそ最も重要な試験といえます。
以下に、「人事委員会面接」の特徴を3つ挙げます。
【特徴1】特別区の面接は長い!(約40分間)
一般的な公務員試験の面接は20分~30分程度ですが、特別区の面接は約40分間と非常に長いです。
集団面接ではなく個別面接であり、1人の受験生に対して3人の面接官がそれぞれ質問します。
また、質問への回答に対する追加の質問や「(回答が)他にはありますか?」といった鋭い質問が多く、一人ひとりの資質がじっくりと吟味される面接です。
そのため、受験生は単なる”一問一答”のような面接準備では太刀打ちできません。
志望動機や自己PRを中心に、自信をもって「語れる」準備をしておく必要があります。
【特徴2】面接が最終合格&順位に大きく影響する
特別区経験者採用では、論文試験(1次試験)と面接(2次試験)で合否が決まります。
配点は公表されていませんが、面接時間の長さからも面接の比重が大きいと想定されます。
さらに重要なのは、受験生は”最終合格”だけでは喜べないということです。
なぜなら、
✓どの区から面接に呼ばれるか分からない(下位合格者は希望区以外から呼ばれる場合あり)
✓まれに区面接で落とされるケースがある
このような事情があるからです。
✓希望した区から面接に呼ばれるか
✓万が一、区面接に落ちても他の区面接に呼ばれるか
これらは合格順位に左右されます。
したがって、「ぜひ特別区に入庁したい!」という人は面接対策を万全にし、上位合格を目指しましょう。
【特徴3】面接の質問はある程度パターン化されている
大規模な自治体の場合、面接の質問は例年、ある程度パターン化されています。
受験生が多いということは、面接官も多く必要になります。
人事課の職員だけでなく、現役管理職などの他部署の職員が面接に関わることになるんです。
面接ブースごとに質問内容が大きく違えば、試験の公平性が失われてしまいます。
そのため、面接官の手元には人事課が事前に準備した「質問例」が置かれていると考えられます。
結局、毎年の人事委員会面接では、ある程度パターン化された質問が聞かれます。
ですから、過去の受験生が面接で実際に聞かれた頻出質問には、即答できるようにしておきましょう。
2.特別区経験者採用の面接で実際に聞かれた7つの質問【準備のヒントも】
毎年多くの特別区受験生にご利用頂いているASK公務員には、特別区面接情報の蓄積があります。
ここでは、特別区経験者採用でよく聞かれる質問の一部をご紹介しましょう。
職務経歴書と矛盾なく、簡潔明快に答えられるよう練習しておいてくださいね。
【質問1】特別区の志望理由を詳しく教えてください
職務経歴書の1つ目の質問で、同じことが聞かれています。
職務経歴書と矛盾した内容を答えると大減点になるため、職務経歴書を音読してほぼ覚えてしまうのが良い対策です。
ただし、一字一句同じ言葉を読み上げるのは不自然ですね。
職務経歴書は文字制限が厳しく、書き切れていない情報があるはずです。
そこに書ききれていない情報も補足して話せるよう準備しておけば、充実した回答ができるでしょう。
【質問2】職務経験は特別区の仕事にどう活かせるか
やはり職務経歴書に記述した内容と被る質問なので、矛盾のない回答を心がけましょう。
また、特別区の仕事を取り上げる際には、あまり限定しすぎないように注意したいです。
たとえば、受験生が、
「信用金庫で地域の企業を支えてきた。この経験を生かして区では産業振興課で~」
こんな回答をすれば、面接官は、
「他の部署に配属されることもあるが大丈夫かな?」
と不安に思うかもしれませんね。
どの部署でも活躍できる人材であることを示すために、汎用的なスキル(上記の例ならたとえば「相手のニーズをよく汲み取る傾聴力」など)をアピールするとよいでしょう。
【質問3】今の仕事を続けようとは考えないんですか
面接では、現職をポジティブに語る受験生が多いはずです。
そちらの方が自身の魅力をアピールしやすいですし、ネガティブに語って「この人は現職から逃げたいのかな?」と思われるよりもずっと良いです。
ただ、面接官によってはここで、
(そんなによい仕事・職場で能力が生かされているなら、続けても良いのでは?)
と思うようです。
この質問には、たとえば、
「たしかに現職は〇〇というような魅力がある。しかし、これまでの経験を生かし特別区で~」
このように現職を上回る思いや熱意、社会貢献への意欲を伝える答え方ができるとよいでしょう。
【質問4】特別区が抱えている課題は何だと考えるか
この質問は、受験者の行政への理解度や関心の高さを見ています。
また、この質問には「課題式論文」の勉強がそのまま生かされます。
課題式論文については、下記の記事も参考になさってください。
【特別区経験者採用】サクッとわかる課題式論文の対策法
「課題式論文」の序論で、社会状況や特別区の課題への認識を書きますよね。
あの内容を、面接のやり取りの中でスラスラと伝えられるようにしておきましょう。
よく書けた課題式論文を音読しておくと、よい準備になりますよ。
【質問5】あなたの欠点をあえて挙げるなら何ですか
職務経歴書には受験者の長所にスポットが当たっています。
この質問では、職務経歴書に無い内容を聞くことで、受験者のリアルな姿を知ろうとしています。
致命的な欠点は避け、職務経歴書で打ち出した長所の「裏返し」を答えると良いでしょう。
たとえば、職務経歴書に、
✓長所は継続力
✓現職で仕事環境を粘り強く改善した
こんなエピソードを書いた人なら、
「短所は、諦めきれずこだわり過ぎてしまう場面があるところです。」
こんな回答があり得るでしょう。さらにすかさず、
「ただ職場では色々な仕事を並行していますので、それら業務に支障が出ないよう、こだわりたい場合でも自分の中で期限を決めて取り組む、という工夫をして対処するようにしています。」
このように短所を補う努力もアピールすると、良い印象で回答をまとめることができます。
【質問6】特別区以外に受験している自治体はあるか
面接官は受験生が確実に入庁してくれるかどうかを気にしています。
ですから、この質問への回答内容は必ず考えておきたいです。
併願しているとしても、「特別区が第一志望です」というように明確に志望度を答えましょう。
また、「併願自治体はありません」と答える場合にも、
「なぜ他の自治体を受けないのですか?」
と聞かれることがあるので、回答を予め用意しておきましょう。
【質問7】職場では今回の受験のことを伝えましたか
受験生の多くは2次面接の時点では受験を周囲に伝えていないはずです。
ただ、先の質問と同様、面接官は確実に入庁してくれるかどうかを気にしています。
「職場には伝えていませんが、合格次第、伝えます。また現在、担当している業務マニュアルを最新のものに書き改めるなど、個人でできることから引継ぎ準備をしています。」
たとえばこんな回答で、面接官の不安を先回りして解消できるといいですね。
3.特別区経験者採用の面接に勝つ!5ステップ対策法
「面接の重要性は分かったけれど、どうやって対策すればいいのかな?」
「人前で話すのは苦手だし、何から手をつけたらいいのか分からない。」
こんな受験者も多いでしょう。
そこで、効率的に面接準備ができる「5ステップ対策法」をご紹介します。
【ステップ0/事前準備】「全体像」をおさえておく
まず、面接試験の評価項目や基本的な対策法を知っておきましょう。
電子書籍『面接対策完全ガイド』を一読するのがおすすめです(無料です!)。
【面接対策完全ガイド】無料ダウンロード
1000人以上受験生を指導してきた講師のノウハウが詰まった本書の第1,2章を読めば、面接対策の全体像をサクッとつかむことができます。
【ステップ1】「職務経歴書」を音読して覚える
面接官の手元には、あなたがエントリー時に入力した「職務経歴書」のコピーが置かれています。
ですから、職務経歴書の内容から多く質問されると思って良いでしょう。
職務経歴書はWeb提出前に画面のスクリーンショットを取っておき、面接前には何度も音読してほぼ内容を覚えてしまいましょう。
そうすることで、実際の面接で自分の言葉で話せるように準備します。
※万が一、スクリーンショットを撮らずに提出してしまった場合は、大まかでも良いので記入内容を思い出し、再現してみましょう。
【ステップ2】「想定問答集」を作って音読する
「職務経歴書」をもとに「想定問答集」を作成し、音読します。
具体的には、「職務経歴書」コピーで聞かれそうな場所に下線を引くとよいです。
そして自分でQ&A化してみるのです。
たとえば、次の「職務経歴書」下線部について、あなたが面接官ならどんなツッコミ(質問)をしたくなるでしょうか。
✓職務経歴書「自分で考え、自分で行動した経験について」(例)
| 職場で大切な顧客情報シートの紛失騒ぎが短期間に二度起こった。そこで私は情報管理、業務効率化の観点からペーパーレス化を上司に進言し〜(以下、実行してうまくいったという内容) |
私なら、こんな風に思いつく限り質問を書き出します。
✓想定質問
①ペーパーレス化に反対意見は無かったのか?
②それまでペーパーレス化が進んでいなかった理由は?
③すべての仕事はペーパーレス化すべきか(紙の方がいい仕事はあるか)?
: |
そして、これらの質問への答えも書いて、スラスラ喋れるように練習しておきます。
【ステップ3】「模擬面接」を受ける
ステップ2まで対策すれば、「こんな質問が来るから、こう答えて~」というように面接のストーリーができあがってくるはず。
ただ、実際の試験では、思いもよらぬ質問が飛んでくるものです。
その対策としては「模擬面接」を受けるのが最適です。
これまで独学で勉強してきた人も、面接だけは、無理に”完全独学”を目指さない方がよいです。
面接は受験者と面接官の双方向のやり取りで成立するものであり、個人練習には限界があります。
あなたの目的はあくまで、合格することのはず。
その目的に向けて最善と思われる手段を選んでいきましょう!
【ステップ4】「模擬面接」の復習をする
せっかく模擬面接を受けるなら、”受けっぱなし”ではもったいないです。
講師の指導をもとに面接回答を修正していく”復習”にこそ、意味があります。
模擬面接でうまく答えられなかった質問はノートに書き出し、講師アドバイスを生かして回答を練り直しましょう。
そして、その復習をふまえてもう一度、模擬面接にチャレンジできるとベストです。
つまり、模擬面接は1回きりでなく、複数回の受講が効果的です。
ASK公務員なら面接指導に熟達した講師に、時間の限り面接の指導を受けることができます。
公務員試験面接対策講座のご案内
これまで独学だった人も短期間でオンライン受講することが可能なので、本番に向けて悔いのない準備ができますよ。
【ステップ5(1級職の場合)】「3分間プレゼン」対策をする
近年、1級職は「3分間プレゼン」を求められることがあるようです。
この「3分間プレゼン」はⅠ類試験では昔から実施されてきました。
「志望動機」や「自己PR」、「取り組みたい仕事」を3分間でコンパクトに話すというものです。
準備していなければ1,2分で話が終わってしまい、大減点につながりかねません。
準備する過程で「志望動機」や「自己PR」を簡潔明快に話せるようになるので、たとえ「3分間プレゼン」を求められなくても準備する価値は大いにあります。
確実に合格したい人、上位合格を目指す人は必ず対策してほしいです。
「3分間プレゼン」は、ASK公務員講師・尾川直子先生による解説動画があるので参考にしてください。
また、ASK公務員「3分間プレゼン添削」では、特別区に特化したプレゼン原稿添削を受けられます。
特別区面接カード(自己PRシート)・3分間プレゼン添削のご案内
客観的な視点で「3分間プレゼン」をブラッシュアップし、自信をもって面接に臨むことができますよ。
話すことに苦手感のある人や、原稿作り・プレゼン練習にプロのサポートが欲しい人にオススメです!
【ステップ5(2級職の場合)】「事例問題」対策をする
例年、2級職では面接の最初に「事例問題」が出ます。
「事例問題」は面接の最初に行われるため、「事例問題」がうまくいくかどうかは面接官の印象を大きく左右します。
「事例問題」はたとえば、次のようなものです。
| あなたは〇〇課〇〇係の主任である。〇〇係には、あなた以外にA係長、B主任、C係員、D係員、嘱託職員のE係員、今年度入庁したF係員がいる。~(以降、あなた以外の誰か、もしくは係全体に起きている問題が書かれている) |
「事例問題」は次のような流れで行われます。
✓「事例問題」実施の流れ
(1)受験生の前の机に「事例問題」の紙が置かれている
(2)面接官から1分程度で内容把握(黙読)するよう言われる
(3)1分後、「ではこの状況で、あなたはどうしますか?」と聞かれる
(4)質問に答え、そのまま3,4往復の質疑応答を行う |
この「事例問題」は、受験者の2級職(主任)適性を見ていると考えられます。
職場の課題について、「自分がどう考えて動くか」はもちろん、「上司への適切な報告・連絡・相談や、周りの職員とのスムーズな連携が取れる人材か」が問われているのです。
事例の”登場人物”が多く、練習しておかないと内容が把握できずに1分間経ってしまいます。
本番では緊張するので、事例文を指でなぞり、頭に登場人物の”相関図”を思い浮かべながら読むのがコツです。
ASK公務員「公務員試験面接対策講座」では講師の先生と相談しながら、面接練習の内容を決めることができます。
公務員試験面接対策講座のご案内
「事例問題」の練習もできますので、お気軽にご相談ください。
2級職は、職務経験の豊富な受験生が多い試験です。
ハイレベルな面接の成否を分ける「事例問題」の対策も抜かりなく、悔いの無い準備をしていきましょう。
4.まとめ
本記事のまとめです!
✓特別区経験者採用の面接試験の特徴3選
①特別区の面接試験は長い(40分、1対3、鋭い質問多し)
②面接が最終合格&順位に影響(下位合格は採用漏れリスクも)
③面接の質問はパターン化(過去の質問が参考になる) |
上位合格を目指して、頻出の面接質問はしっかり準備しておきたいですね。
そして、実際の面接試験では、こんな質問がよく聞かれています。
✓特別区経験者採用の面接で聞かれた7つの質問
①特別区の志望理由を詳しく教えてください
②職務経験は特別区の仕事にどう活かせるか
③今の仕事を続けようとは考えないんですか
④特別区が抱えている課題は何だと考えるか
⑤あなたの欠点をあえて挙げるなら何ですか
⑥特別区以外に受験している自治体はあるか
⑦職場では今回の受験のことを伝えましたか |
あなたは、これらの質問に即答できるでしょうか。
本記事を読み返しながら、自分らしい回答を準備していきましょう。
✓特別区経験者採用の面接に勝つ!5ステップ対策法
模擬面接は、本番さながら、ASK公務員のプロ講師からマンツーマン指導を受けるのがオススメです!
✓ASK公務員の特別区面接対策
以上です!
皆さんが面接の場で、ご自身の経験や魅力を存分に伝えられるよう、そして夢を叶えられるよう応援しています。

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ