特別区経験者採用では、一次試験で2種類の論文試験が課されます。
(2種類の論文試験=「課題式論文」「職務経験論文」)
本記事では特に、公務員経験のない社会人にはハードルの高い「課題式論文」について解説します。
この記事で、「課題式論文」のポイント、傾向と対策の全体像をつかみましょう。
1.特別区経験者採用では「課題式論文」が合否を分ける!
まず前提として、「課題式論文」の特徴を確認してみましょう。
| ◆「課題式論文」の特徴 ✓ テーマを選べる2択形式 ✓ ただし、大卒程度試験(Ⅰ類)よりも抽象度が高い |
テーマ選択式といっても、取り組みやすい課題ではありません。
むしろ、大卒程度試験(Ⅰ類)よりも抽象度・難易度は高いのです。
これは、過去問を見ると一目瞭然です。
|
令和4年度 【経験者採用】 |
複雑化・多様化する区民ニーズへの対応について |
| 令和4年度 【Ⅰ類】「論文」選択式課題1 |
特別区では、地方分権の進展や、児童相談所の設置に加え、新型コロナウイルス感染症対策により、前例のない課題やニーズが生まれ、区民が期待する役割も、かつてないほど複雑で高度なものとなっています。 特別区がこれらの課題の解決に向けた取組を進めていくには、区民に最も身近な基礎自治体として、自立性の高い効率的な事務運営が重要です。このような状況を踏まえ、区民の生命や生活を守るための、限られた行政資源による区政運営について、特別区の職員としてどのように取り組むべきか、あなたの考えを論じなさい。 |
太字に注目すると、この2問はかなり近い内容です。
しかし、経験者採用試験の「課題式論文」では、シンプルにテーマのみ与えられています。
Ⅰ類のように、テーマの前提となる社会状況などの補足が一切ありません。
経験者採用の受験生は自身でテーマの背景から論じていく力が必要なのです。
このような試験では、対策している人・していない人との間で大きく差が開くでしょう。
逆にいえば、ちゃんと対策した人は、それだけ合格が近づくといえます。
2.「課題式論文」の過去問テーマ&今後の出題予想と対策
では次に、「課題式論文」の過去問テーマと、そこから分かる傾向・対策を見ていきましょう。
2-1.「課題式論文」の過去問テーマ
過去3年間の論述テーマは次のとおりです。
| 令和5年度 | ①図書館機能の充実について ②これからのイベント実施のあり方について |
| 令和4年度 | ①シティプロモーションについて ②複雑化・多様化する区民ニーズへの対応について |
| 令和3年度 | ①インターネットを活用した誰もが利用できる行政手続に向けた取組について ②持続可能な財政運営と区民サービスについて |
【参照】試験問題及び正答の公表(特別区人事委員会)
パッと見たときに、「狭いテーマと広いテーマの組み合わせになっている」ということが分かると思います。
テーマの広さで分類してみましょう。
| 狭いテーマ | 図書館機能の充実(R5) シティプロモーション(R4) インターネットを活用した誰もが利用できる行政手続に向けた取組(R3) |
| 広いテーマ | 複雑化・多様化する区民ニーズへの対応(R4) 持続可能な財政運営と区民サービス(R3) |
| 中間的テーマ | これからのイベント実施のあり方(R5) |
どちらかというと広いテーマの方が書きやすい、という受験生が多いようです。
(狭いテーマの場合、そのテーマへの知識が前提になるからですね。)
広いテーマで論文を書く場合にも、行政運営全般への知識及び理解が必須となります。
2-2.今後の出題傾向【予想と対策】
ただ、ここで皆さんに朗報があります。
それは、「広いテーマほど、過去問でくり返し聞かれている」ということです。
これも表にまとめてみました。
| 出題されたテーマ | 過去の類似テーマ |
| 複雑化・多様化する区民ニーズへの対応(R4) | 住民意識の多様化と自治体職員の役割(R2) 区民ニーズの把握と施策への反映(H28) |
| 持続可能な財政運営と区民サービス(R3) | 最少の経費で最大の効果を生む区政運営(H29) 区民から喜ばれる行政サービスの提供(H26) |
| これからのイベント実施のあり方(R5) | 地域コミュニティの活性化について(R1) 地域イベント開催にあたっての住民要望の調整(H27) |
※R5年度は少し限定的なテーマ(イベント実施)ですが、”地域活性化”と広げて考えれば、やはり過去に複数類題があります。
このように、「課題式論文」は過去問テーマがくり返し出題されます。
こうした傾向は一貫しているので、「過去問で合格答案を書けるようにする」ことこそが合格の近道です。
3.「課題式論文」で手堅く合格点を取る勉強法【3ステップ】
では、「過去問で合格答案を書けるようにする」には、どうしたらいいでしょうか?
3ステップで解説します。
3-1.【ステップ①】今すぐ論文の「型」を身につける
まず、公務員試験の論文の「型」を学んだことがない人は、その「型」を身につける必要があります。
| ◆「型」を身につければ… ✓ 主張がスッキリ伝わる論文を書けるようになる ✓ 制限時間内に論文を書き上げられるようになる |
採点者は、短い時間で大量の答案を読みます。
論文の内容が良くても、読みづらい答案ではマイナス評価につながりかねません。
「型」を身につけることで、あなたの主張が明快に伝わる論文になります。
また、常に「型」を意識して書くことで迷わず書き進められる効果もあります。
特別区の経験者採用試験では、90分で「1200字以上~1500字程度」が条件。
試験中に論理展開を迷うと、字数を満たせずに試験が終わってしまいます。
ASK公務員では、電子書籍「はじめての小論文・作文書き方Book」を無料で差し上げています。
論文の「型」を身につけるのに最適な教材なので、学習のはじめにぜひ手に入れてください。
(特に最後のワークはⅠ類の過去問が題材ですが、「課題式論文」対策にも非常に有用ですのでぜひ活用してください)
3-2.【ステップ②】実際に書きながら、足りない知識を身につける
基本的な「型」を身につけたら、過去問を解いてみましょう。
| ◆初めて過去問を解くときのコツ ✓ 制限時間を気にせずに解く ✓ 参考文献を参照しながら解く |
いきなり時間内に書き上げることは難しいので、じっくり時間をかけて書くとよいです。
また、「型」が身についても行政運営の基礎知識がないと書き進められません。
そこで、手が止まったら参考文献を見ながら書くのがおすすめです。
参考書は、「特別区職員ハンドブック2023」(特別区職員研修所/ぎょうせい)が便利です。
この本の「第Ⅲ編 組織と仕事」を理解すれば、広いテーマはほぼ書けるようになります。
※本書は実際に特別区の職員研修で使われている書籍です。
| ◆注意 「まず、たくさん勉強してから論文を書き始めよう」とする人が多いですが効率が悪いです。 たとえば、紹介した書籍1冊だけでも750ページもあり、いきなり読み通そうとすると挫折します。 結局、「書くためにどの知識が特に必要か」は、実際に問題に取り組んで初めてわかるものなのです。 |
3-3.【ステップ③】何も見ず、時間内に解けるように練習を重ねる
時間をかけて何本か論文を書くと、自力で書ける部分が増え、スピードも上がってきます。
次は、だんだん本番に近い条件で過去問演習を重ねるとよいでしょう。
| ◆たとえば… ✓ 100分(実際の試験時間プラス10分)で解いてみる ✓ 参考文献を見られる回数を限定する(「3回しか見ない」というように) |
そして、いよいよ本番通りの条件(90分、参考文献なし)で書き上げる練習を重ねます。
直前期には、見直しの時間も想定して、80分で書き上げられる力をつけているのが理想です。
◆客観的なフィードバックを得られると論文力はグッと伸びる
ステップ②や③で「自分の答案は合格点?」「点をさらに伸ばすには?」と疑問がわいてきます。そんなときは客観的なアドバイスをもらうのが有効です。たとえばASK公務員のオンライン添削。実績豊富な講師があなたの答案を丁寧に添削し、合格に必要なポイントをレクチャーしますので、試験当日までの学習の方向性が明確になりますよ。
4.まとめ
| ◆課題式論文は… ✓テーマを選べる2択形式だが、大卒程度試験より難しい ✓テーマには狭いテーマと広いテーマがある ✓広いテーマほど、過去にくり返し問われている傾向がある ✓合格点を取る勉強法は①論文の「型」を学ぶ②書いて知識を身につける③本番の条件で解く ✓論文の「型」は無料で学べる⇒「はじめての小論文・作文書き方Book」無料ダウンロード ✓家でプロの論文添削が受けることもできる⇒オンライン添削 |
学習内容が明確な教養試験とちがって、論文試験は「ついつい後回し」にされがちです。
しかし、特別区経験者採用では、論文試験こそ合格を左右する重要科目。
必ず合格したい人は、決して後回しにせず、今日から学習に取り組みましょう。
まずは、論文の「型」を身につけるところから。
皆さんの頑張りを応援しています。

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ


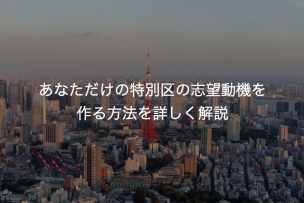
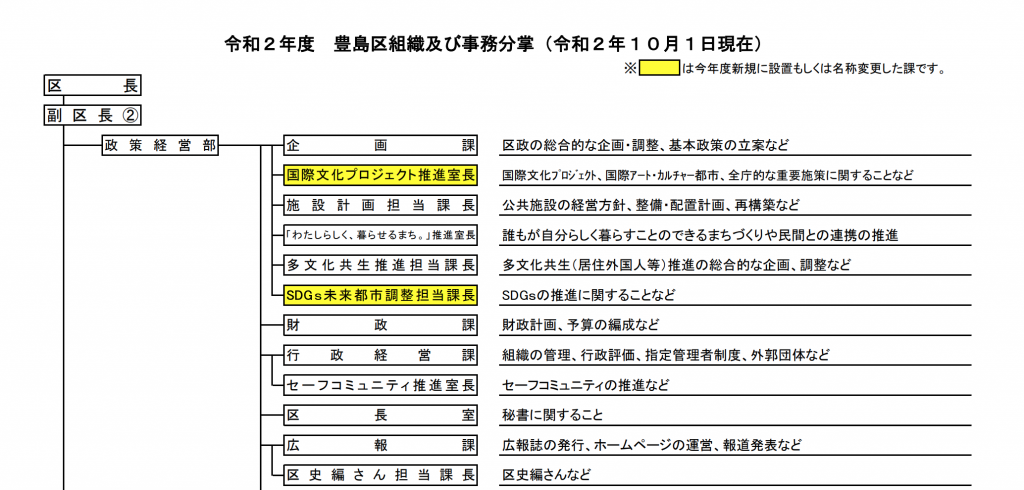
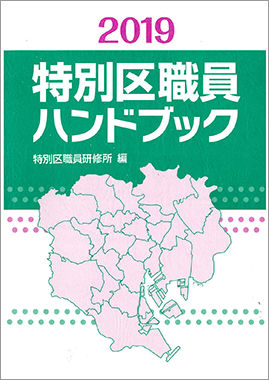

![地方上級・国家一般職[大卒]・市役所上・中級 論文試験 頻出テーマのまとめ方 2017年度](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/513k63%2BjUhL._SL160_.jpg)







