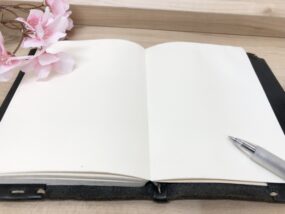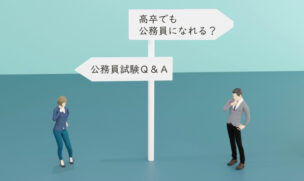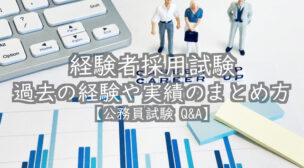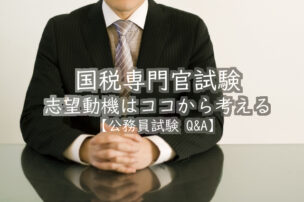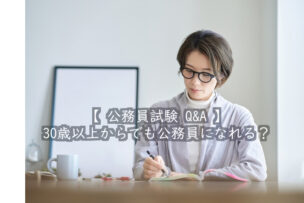こんにちは。ASK公務員/究進塾 編集部です。
今回は、ASK公務員/究進塾のサイトへのお問い合わせの中から「市役所への志望動機について」にお答えする第2回目です。
市役所への志望動機を作るにあたり、「市の課題を見つけることが大切」ですが、今回はこの「市の課題」というのをどのように見つければいいのかについてです。
課題のピックアップ
前回「“〇〇市 課題” で検索すると関連するサイトが出てくる」と紹介しましたが、そのような検索を行うと課題はいくつも上がってきます。
その時にどういう課題をピックアップするといいのかというと、自分に関連したものです。この方が話しやすくなります。
ピックアップの例
例えば、ヤングケアラーとまではいかなくても、ご家族の介護を経験した人なら「〇〇市は高齢者人口の伸び率が高い」といった課題に目を向けるのは当然でしょう。
部活動の練習や大会、市の体育館を利用した人であれば、「市の施設の老朽化」といった課題が目に留まるでしょう。
合格者の例
以前、横浜市に合格した人の例を紹介します。
その方は横浜市内のスーパーマーケットでアルバイトをしていたのですが、横浜市が野菜の産地であるということが市民にもいまひとつ知られていない、という気づきがあったそうです。
| 参考:横浜市の野菜生産
横浜の農業は野菜、果樹、畜産、花きと、バラエティに富んでいますが、その中でも、野菜生産が最も多く、面積では約7割を占めます。 最も生産量が多いのが、キャベツで、全国での生産量が10位となっています。(平成18年産。全国約1,800市町村中の順位。 市内の野菜生産量は約6万トンで、横浜市民の野菜消費量の約18パーセントに当たります。 |
このように、自身の生活やこれまでの人生を振り返りつつ、どのようなことに困ったのか、考えさせられたのかを思い出してみるといいでしょう。
この方法だと、その市に縁もゆかりもなくても、志望動機を作りやすくなります。
縁のある人に聞いてみる
志望している市に友人や知り合い、親戚が住んでいるなら、住み心地を訪ねてみましょう。
尾川講師は特別区内に住んでいるため、特別区志望だけれど住んではいないという受講生から「困っていることはどんなことですか?」とよく聞かれるとのこと。
「目の前の人の困っていることに対し、行政の一員としてどのように解決していきたいのか」ということを考えつつ、志望動機を作っていきましょう。
そうは言っても、簡単にはできないのが志望動機です。
何も思いつかないという方はASK公務員/究進塾にどうぞお問い合わせください。
これまでや現在を伺いつつ、ご自身、そしてもちろん面接官にも納得していただける志望動機を一緒に作っていきます。
おわりに
この記事は、ASK公務員/究進塾の担当、尾川直子講師の解説動画を元に作成しています。講義・講師の雰囲気を知りたい方は、ぜひ動画も併せてご覧ください。尾川講師のプロフィールはこちら。

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ