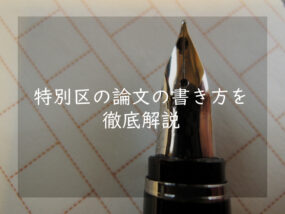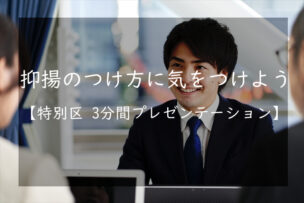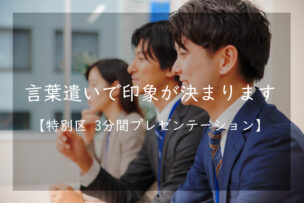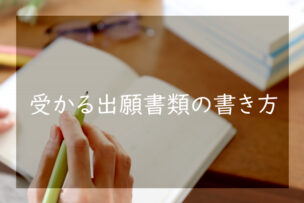こんにちは。ASK公務員/究進塾 編集部です。
今回は、実際に特別区に合格した方の事例をご紹介します。
◆ この記事のポイント
・経験を志望動機にどう繋げるか
・対策する上でポイントになる部分とは
・受講開始時期やペースの目安は
この記事は、ASK公務員/究進塾の担当、尾川直子講師の解説動画を元に作成しています。講義・講師の雰囲気を知りたい方は、ぜひ動画も併せてご覧ください。尾川講師のプロフィールはこちら。
◆合格事例①:新卒枠(社会人)
この方の特徴
ご紹介する事例の、1人目の方の特徴です。
・社会人
・20代後半
・男性
・大学卒業
・就職、転職経験あり
この方は大学を卒業後、公共性の高い民間の職場に就職していました。何年か勤めた後、一般企業に転職した経験を持っています。
社会人でも新卒と同じ枠に
このように社会人経験が数年ある場合でも、経験者採用の枠を受験するには年齢が若いため、新卒枠で受験することになります。
この場合、新卒の方たちとの差別化を図ることが、大事なポイントとなります。
対策したポイント
・現役の学生とは違う雰囲気にする
・社会人らしさを出すこと
・特に志望動機や3分間プレゼンテーションは、働いている経験を活かせる内容にするために時間をかけて準備
“なぜ公務員に転職を”を考える
この方は、2つ目の勤務先では、災害対策を行う部署で働いていました。そのため「勤務先で得られた経験を特別区でどのように活かせるか」について考えてもらいました。
とはいえ、2つの事柄を無理やり結び付けようとすると不自然になってしまいます。そこで「企業で災害対策にあたっていたのに、なぜそれを特別区で行いたいのか」ということを深めました。
・民間と行政
・会社員と公務員
これらの違いを考えていくことにもつながるので、これは非常に有効なワークです。
さらに、特別区で必要とされる災害対策についても、「どのように進めていくべきか」を話せるように準備をしました。
社会人が受験する上で気を付けるべき点
社会人の方は、自分のしてきたことを話せば十分な内容になります。
・勤務先で取り組んできたこと
・勤務先で努力したこと
・達成感を得られたこと
・チームワークを発揮したこと など
こうした自身の経験が含まれる内容は、比較的スムーズに話せるはずです。しかし、以下のような質問に答えていくのは難しい傾向にあります。
・なぜこのタイミングで転職したいのか
・なぜ転職先に公務員を選ぶのか
・なぜ特別区なのか
こうした内容をしっかりと固め、何度も面接レッスンをし、自然な笑顔で話せるようになっていったことが、高い順位での合格に繋がったのではと思います。
特別区の新卒枠について
2023年度の場合、「1992年4月2日以降に生まれた人」は受験できます。
30歳近くになっていたとしても、臆せずにチャレンジしていただきたいと思います。
◆合格事例②:社会人経験者採用
次に、特別区の経験者採用に合格した方の事例をご紹介します。
経験者採用の場合は、論文が2題出題されるため、それぞれに対策する必要があります。
この方の特徴
・社会人
・30代前半
・女性
・高校卒業
・企業に勤務(事務、接客)
彼女は高校卒業後に就職し、事務と接客をして働いていました。
入塾・受講のペースと内容
彼女がASK公務員/究進塾に入塾したのは、経験者採用1次試験のちょうど1年前です。
まず、月に2回のペースで論文対策の授業を受講し、過去問を中心に論文を書く練習を積みました。面接対策に関しては、1次試験が終わってからすぐに開始しました。
論文の対策
この方の場合、それまでレポートなどを書く機会に乏しかったため、論文を書くことに慣れるまで少し時間がかかりました。
それでも1年前から始めただけあって、試験の約2ヶ月前にはほぼ仕上がりました。講師から見ても、本番もよほどのことがない限り良い答案が書けそうだ、という水準にまでなりました。
出願書類の作成
論文対策と並行で、出願の書類作成にも時間をかけました。
良いものを提出できるようにするために、職場でのいろいろなエピソードを整理していきました。
経験者論文の対策をしている中で、すでに職場でのエピソードをいくつも使っていたため、書くネタに困ることはありませんでした。
面接の対策
彼女の場合、提出した書類が良い内容だったこともあって、スムーズに面接対策に入れました。
・なぜ公務員に転職したいのか
・なぜこのタイミングで転職したいのか
・なぜ特別区の職員になりたいのか
・職場でどういう仕事や経験をしてきたのか
こうした内容を中心に、模擬面接とフィードバックを繰り返しました。
特別区の新卒枠について
面接対策はいつからすべきか
経験者採用の場合、1次試験の合格発表日から2次試験の日まで、あまり日にちの余裕がありません。
1次試験である程度手応えがある場合、早めに対策を開始することをおすすめします。
区面接の対策
人事院面接に通過後、区面接があります。この方は幸いなことに、第1志望の区から連絡をいただきました。
なぜその区を志望したのか、その区で何をどう取り組みたいのか、志望動機をしっかりと作るためには、以下のような行動が必要です。
・町歩き
・区の政策を調べる
・志望動機をしっかり作成
特別区の新卒枠について
経験者採用を利用する方の困難
経験者採用を受ける方は、勉強する期間が長くなりがちです。仕事をしながら受験勉強をせざるを得ないからです。さらに論文に苦手意識がある場合はなおさら大変です。
1年前から準備を始めることをおすすめします。
おわりに
ASK公務員/究進塾では、特別区の対策に関しても、丁寧に指導を行っております。
◆尾川講師の授業の特徴
尾川講師の授業では、新卒の方々とはまた違う魅力がアピールできるよう、お手伝いをしております。面接対策も、内容をしっかりと固め、自然な笑顔で話せるよう、授業内で何度も練習をしていきます。
受講にご興味のある方は、「無料体験授業お申込みフォーム」からお気軽にお問い合わせください。

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ