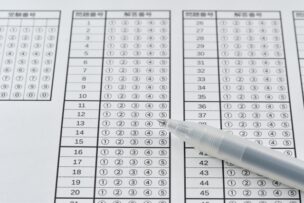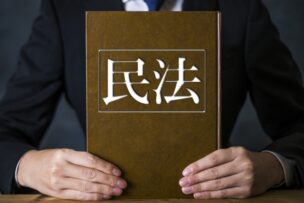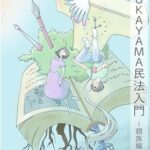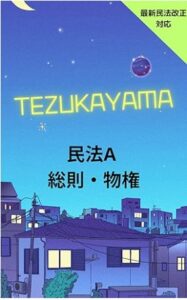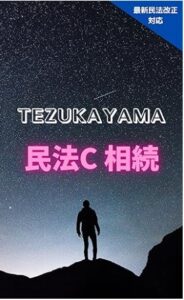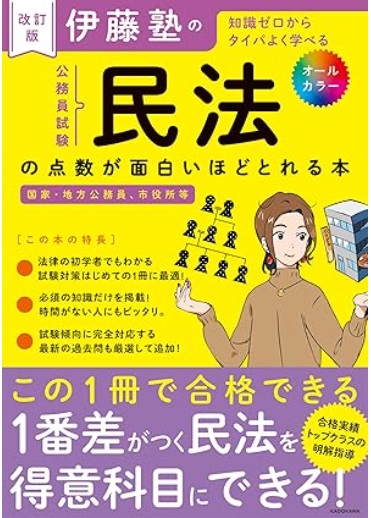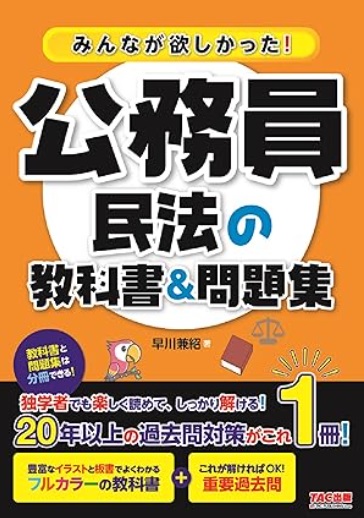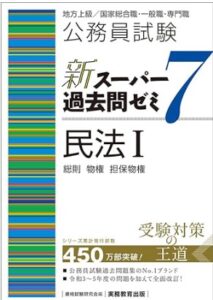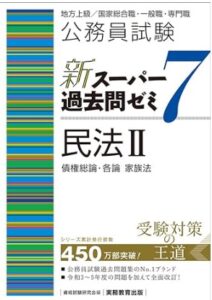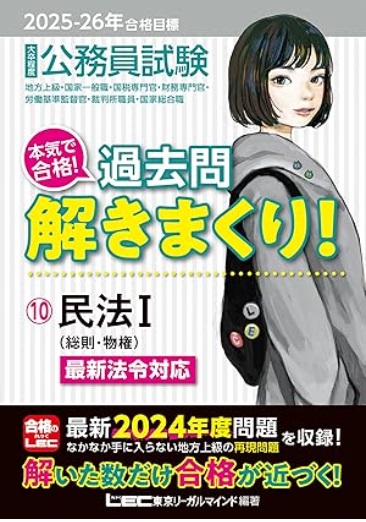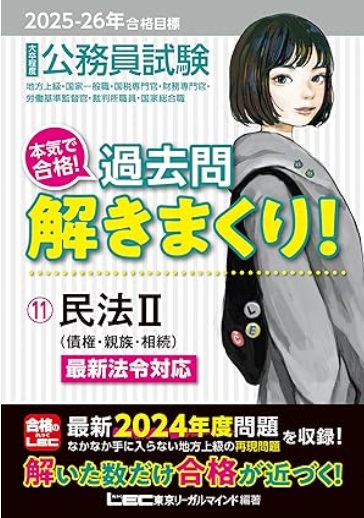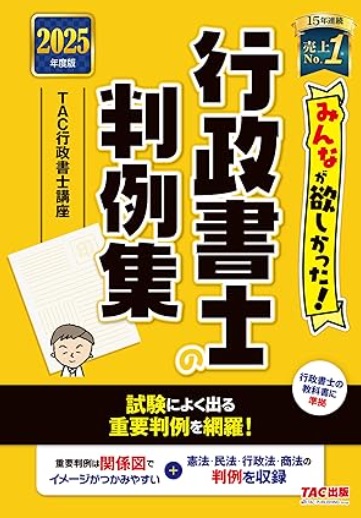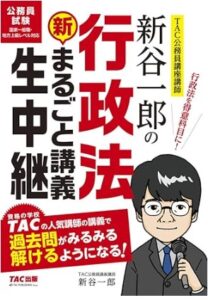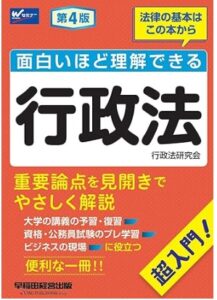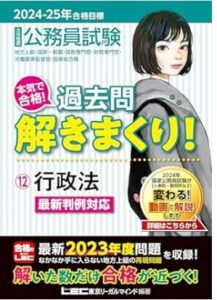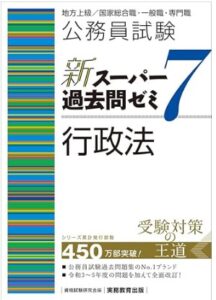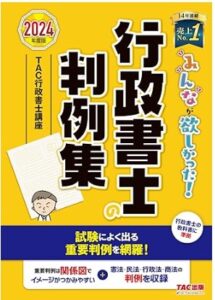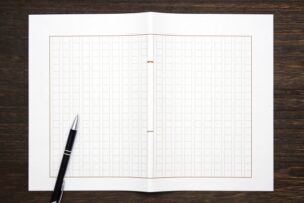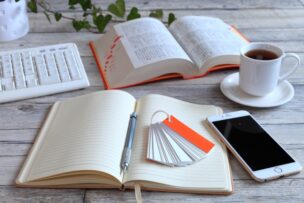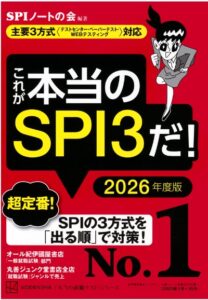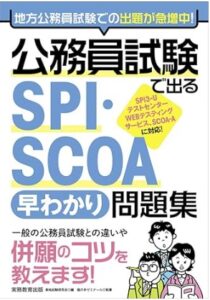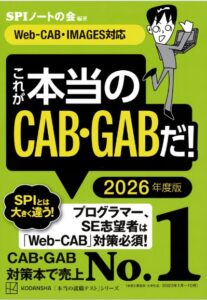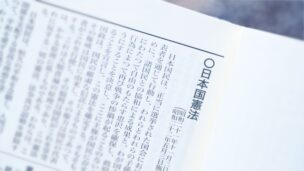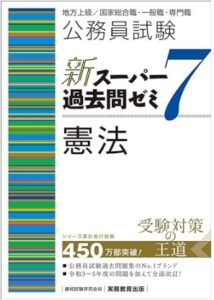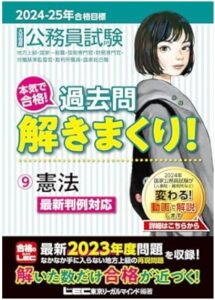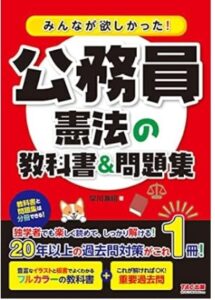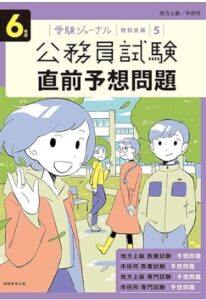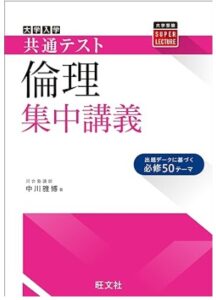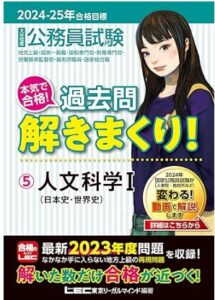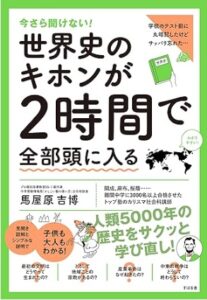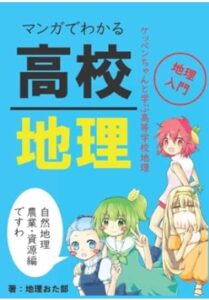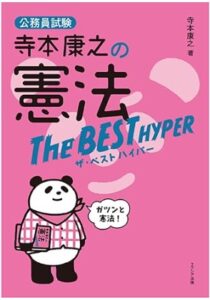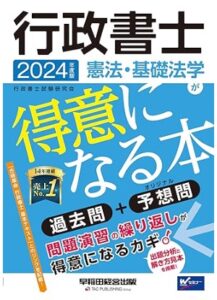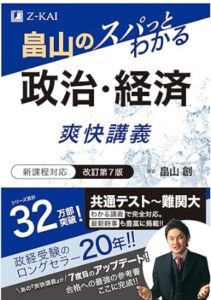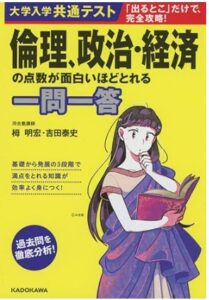1.はじめに
大学卒業程度試験は、従来1年に1回、6~7月に実施するのが一般的でした。しかし、近年はこの通常試験に加え、3~5月にも早期試験を行う自治体が増加傾向です。
早期試験は、文字通り「早期枠」といったり、「先行実施枠」や「アピール試験型」、「特別枠」など様々な名称で行われています。
他方、ほとんどの早期試験において、一次試験は、SPI3やSCOAなどが実施されるという特徴があります。これらの筆記試験は、民間企業でも使われているものであり、特別な公務員試験対策は不要です。
より具体的にいうと、憲法や民法、経済学などの専門科目はもちろん、数的推理・判断推理・社会科学・人文科学・自然科学などの公務員で出題される教養試験を勉強しなくて済みます。これらの勉強をするのは辛いですから、「ラッキー」と思うかもしれません。
しかし、そうとも言えない留意点があります。本記事では、これを3点にわけて説明していきます。安易に試験形態を選択せず、こちらの留意点を踏まえた上で、試験内容を選び試験対策に励んで頂きたいと思います。
なお、本記事では、SPI3やSCOAなどを実施する「民間筆記試験型公務員試験」と称します。
2.「民間筆記試験型公務員試験」3つの留意事項
それでは、3つの留意事項を確認しましょう。
(1)倍率が上昇する可能性が高い
そもそも、なぜ「民間筆記試験型公務員試験」を導入したのでしょうか。もちろん、自治体ごとの事情はあるでしょうが、総じていえば、公務員試験受験者の減少です。
現代の日本は少子化が進行しています。これによる人手不足は官民どちらにとっても深刻です。そのため、新卒者等の就職希望者にとって、民間企業での就職は、就職氷河期と呼ばれた時期に比べれば易しいことになります。
となると、わざわざ公務員試験だけにしか使えない筆記試験内容の勉強をしなくても、民間企業を受けて就職しようと就職希望者は考えてしまいます。つまり、公務員試験の受験が選ばれなくなるわけです。
この倍率低下は、民間企業からの内定を貰えるような人材(=一定の魅力があるから内定が貰えると考えればそれなりに優秀と考えられる人材)が、公務員に集まらなくなると考えれば、人材の質低下をも予見させます。
ということで、民間企業を受けようとしている層にも公務員試験受験選択をして欲しくて、「民間筆記試験型公務員試験」の導入が高まっていると言えます。そして、現に、同じ筆記試験なら、受けてみようかなと思う層は一定数います。なぜなら、公務員試験には民間企業よりも手厚い身分保障と、民間企業では見られるところが少なくなってきた年功序列と終身雇用という人事システムが残されているからです。
以上の議論からも分かる通り、「民間筆記試験型公務員試験」は、そもそも公務員受験者数増加を目的としていますし、受験負担が少ないのに公務員の魅力は変わらずあるなら「受験をそこまで考えていなかったけど、受けてみるか」と受験対象者を振り返らせることが可能であるため、倍率が上昇するわけです。
実際、令和6年度兵庫県の大卒・早期SPI型の倍率は69.3倍です(20人募集のところを1385人申し込み)。一方、同県の大卒・通常枠の倍率は7.9倍です(104人募集のところ822人申し込み)。こうした、倍率差を出す自治体は大変多いです。
(2)受験負担が思いのほかに大きい
2点目は、受験負担が想定よりも大きくなる可能性が高くなるということです。これには2つの意味合いがあります。
第1は、3~5月に受験となることで、民間企業の就職活動と時期が重なるため、並行作業が大変になるということです。
もちろん、従来からの公務員試験だって遅いわけなので重なります。しかし、この重なりは民間企業が説明会参加や面接試験なのに対し、ひとまずは6・7月に向けた筆記試験ですので、準備する性質が異なります。
これは私の実体験でもありますが、民間企業の面接など人とのやりとりを適度に挟みながら、それ以外を公務員試験勉強に打ち込むと、どちらにとっても良い気分転換になる場合があります。そして、公務員試験の面接は7~8月となりますので、その頃には民間企業の活動がほぼ終わっており、公務員用の面接試験に集中できます。
しかし、「民間筆記試験型公務員試験」の場合は、民間企業と同時並行で、民間企業で行うのと同じ作業である、面接試験で話す内容の検討並びに自治体研究(≒企業研究)をしなくてはならず、どの受験先が何だったか等が混乱したり、覚えきれなかったりする可能性が高まります。
第2は、「民間筆記試験型公務員試験」が人物重視であることによります。(1)で述べた通り、高倍率の試験である一方、SPIなどの筆記試験は公務員試験より優しいことから差がつきにくいため、必然的に人物重視となります。
これは、集団面接・個人面接・グループディスカッション・プレゼンなど多様な人物試験があることからも伺えます。これらの試験でふるいにかけて、合格者を出すわけですね。
なお、民間企業のエントリーシートと同様に、自己アピールや志望動機、入ってからやりたいことなどを記載するシートの事前提出もあります。これは、なぜか手書きを要求する自治体も多いです(PC作成が可のところもありますが)。この書類も合否を左右します。
そして、これらの提出書類や人物試験は、公務員の仕事という特有性を理解しながら自身を売り込む内容で書くため、民間企業の使いまわしが困難です。もちろん、大学時代に、売り込める内容につながるような経験も必要です(サークル、アルバイト、インターンシップ、ボランティア、ゼミナール活動などで相応の経験をしているかという吟味も求められるということです)。
2点目をまとめると、自身のキャリアを見つめつつ、重視されている人物試験を突破できる言動の準備と、実際に適切な表現ができるよう練習することが必要で、これを民間企業の就職活動と並行して行うという負担があることに留意しなければなりません。
(3)公務員試験の併願は困難になる
令和6年現在、国家公務員一般職や国家専門職試験など国家公務員系において、「民間筆記試験型公務員試験」の区分はありません。
そして、地方自治体の「民間筆記試験型公務員試験」は、SPIの試験自体はテストセンターを利用するので近隣自治体と日程の重なりは少ないですが、人物試験時期は同じである場合が多いです。つまり、人物試験の段階で日程が重なりどちらかしか受けられないことが近隣自治体だと多くなるというわけです。
こうして、公務員試験の受験数が「民間筆記試験型公務員試験」だけの利用を考えると増やしにくくなります(日本全国いろいろ受けるつもりなら大丈夫ですが)。
これは、「縁あるところで公務員になりたい」と考え、いろいろ受けたい人にとっては、結局、公務員試験内容の筆記試験勉強をしないといけないことを意味します。こういう人にとって、わざわざ高倍率で、人物試験の準備が重たい「民間筆記試験型公務員試験」を受けるメリットは少なくなるでしょう。
3.おわりに
公務員試験用の学習は、多科目で難易度もそれなりに高いため、正直避けられるなら避けたいものです。これをしなくても良い「民間筆記試験型公務員試験」は魅力的に感じることでしょう。
しかし、倍率は、皆同じことを考えるため跳ね上がります。また、公務員になる人物として売り込む準備をして、実際に振る舞えるように練習することを、民間企業の就職活動等と並行して行う負担もあります。さらに、公務員試験併願は少なくなる懸念があります。
こう考えると、安易に「民間筆記試験型公務員試験」を目指すのは得策ではありません。公務員が本命なのであれば、倍率、負担感・併願可能性を考慮すると、従来型の公務員試験で臨む方が得策となります。
他方、「民間企業に軸足を置いて就職活動していたが、その中で公務員がよくなったけれど、今さら目指せないだろうな」のように思っている方にとっては、筆記試験の準備が少なく済むため、「民間筆記試験型公務員試験」の受験は悪くない選択肢になります。
以上を踏まえつつ、ご自身の受験計画を立てて頂ければと存じます。
なお、究進塾では、公務員試験対策の学習相談を承っています。また、個別面接などの人物試験対策も実施しています。よろしければご利用をご検討ください。

 個別指導講座
個別指導講座 お問い合わせ
お問い合わせ